はじめに
「社内SEが、なぜ運行管理者資格を取ったのか?」という問いに、即答できる人は少ないかもしれません。ITと物流は別物、という認識が一般的です。しかし、私がこの資格を取得したのは「物流の現場で見た、ITの限界」がきっかけでした。
倉庫から出荷された商品が、最終的にどう運ばれて、どう届けられているのか──その「現場の最後の1マイル」を知らずに、仕組みだけで語ることはできないと感じたのです。この記事では、社内SEとして運行管理者資格を取るまでの経緯と、その取得がもたらした“視点の変化”について詳しく語ります。

まさかITの人が、運行管理者を受けるなんて…!でもね、現場を知るって、本当に強い武器になるんです😊
きっかけは“現場の見えなさ”
私はこれまで、WMSや販売管理システムの設計を社内SEとして担当してきました。ピッキング指示・出荷管理・納品伝票の発行まではITで管理できる。けれど──「その先」がずっとブラックボックスだったのです。
「トラックが遅延した」「ドライバーが積み忘れた」「納品先で時間が合わない」──そんな声は現場からよく聞こえてきます。でも、それを“仕組み側”から解決できるだけの知識や理解が、自分にはない。そう痛感したとき、運行管理の知識が必要だと思いました。
試験に向けてやったこと
運行管理者資格(貨物)は国家資格ですが、合格率は30~40%。侮れない試験です。私はまず参考書を1冊選び、1日30分でも必ず目を通すことを続けました。過去問演習はスキマ時間にスマホで。出題傾向はある程度決まっているため、出題頻度の高い項目に集中して取り組みました。
特に苦労したのは法令系の問題です。実務とは少し離れているので暗記要素が多く、最初は意味がよくわからないまま丸暗記していました。が、実際の業務に照らし合わせながら読むことで、少しずつ頭に入ってくるようになりました。
資格を取って見えた世界
運行管理者の資格を通して得られたのは、「トラックの世界の論理」でした。たとえば、1日に運転できる時間、休憩のルール、拘束時間の制限──これはまさに「仕組み設計」に必要な情報です。
現場では「なぜ15時までに積まないといけないのか」といった“感覚”が支配しています。でもSEがそれを理解して設計に盛り込めば、「この処理は14:30までに終わらせる」「ラベル発行タイミングを前倒しする」といった、実効性のある改善が提案できるようになるのです。
まとめ
「現場を知る」ことは、SEとしての武器になります。特に物流分野では、ITと現場の感覚のズレが業務に大きな影響を与えます。運行管理者資格は、そうしたズレを埋める“言語”の一つです。
資格を取ったからといって、すぐに何かが変わるわけではありません。でも、現場との会話が噛み合うようになった。設計段階で「その時間では運転者が間に合わない」と気づけるようになった──その積み重ねが、社内SEとしての信頼につながっていくのだと思います。
運行管理者の資格は、SEにとっては“異分野”かもしれません。けれどそれが、仕組みと現場をつなぐ強力な視点になる──それを私は、実感として伝えたいです。
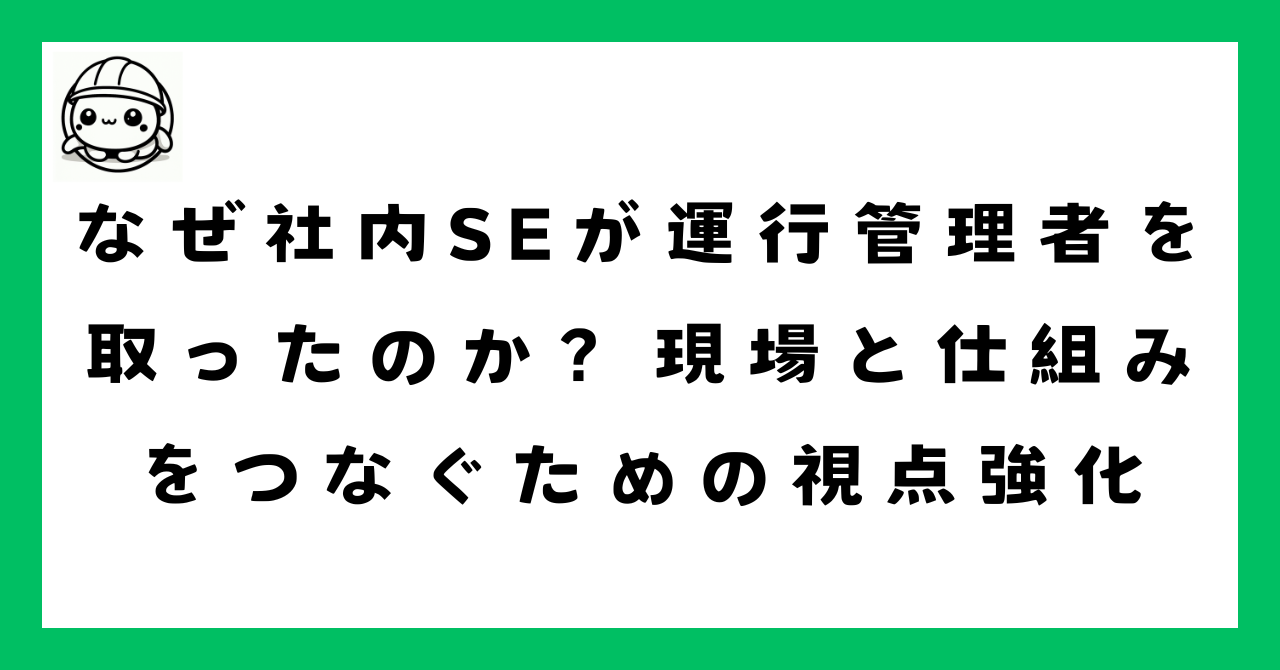
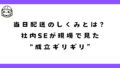
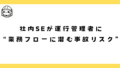
コメント