はじめに
物流業界における事故リスクは、現場だけにあるわけではありません。実は、社内で組まれている業務フローそのものにも“事故の種”が潜んでいます。私は社内SEとして日々システム改善に取り組む中で、運行管理者資格を取得し、はじめてこのリスクの実像に気づくことができました。
この記事では、運行管理の視点を持った社内SEだからこそ見えた「事故を誘発しうる設計ミス」や「危険を無意識に拡大している業務プロセス」について、具体的な例を交えて解説します。

現場の声を“仕組み”に反映させるって、ほんと大変。でも、そこにこそSEの価値があるんだと思います😊
フローに潜む“時間の罠”
社内SEとして出荷システムを構築していた頃、出荷締切時刻を「15時」と設定していました。しかし、現場では14時には作業を終え、ドライバーに引き渡す必要があるという暗黙ルールが存在していたのです。
結果、締切ギリギリの出荷データが現場を混乱させ、積載遅れが発生し、ドライバーが焦って運転する…という悪循環を招いていました。これは「締切時刻の設計ミス」が原因の一つでした。
“負荷の分散”が事故を防ぐ
出荷指示が1時間に集中するような設計になっていないか。ドライバーの拘束時間が業務フロー上で延びていないか。運行管理者としての視点を持つと、「どのタイミングに無理があるか」が見えてきます。
システムのロジック上は正しくても、人が動く現場では「ちょっとの無理」が蓄積して、ヒューマンエラーの原因になります。操作フローの見直し、通知の前倒し、ピッキング順の最適化など、小さな調整が安全性に直結します。
“安全”は設計でつくれる
事故の発生はドライバーや現場作業者の責任とされがちですが、SEが構築した“仕組み”にも原因があるかもしれません。運行管理の知識があると、「この工程は待機時間が長すぎる」「回送運転が増えている」「車両管理が属人化している」といった視点を持てるようになります。
たとえば、「14時間ルール」を守るには休憩と終業を意識した配車が必要です。システム側でアラートを出す、または締切時刻を調整することで、結果的に事故リスクを下げることも可能です。
まとめ
運行管理者資格を取得して最も大きかったのは、「業務フローに対する見方」が変わったことでした。業務を“効率”だけでなく“安全”という軸でも見るようになり、SEとしての判断にも深みが出てきました。
事故は現場のせいではなく、フローのせいかもしれない──。そう思えるようになることが、システム担当者として“現場と一体になって考える”第一歩だと思います。安全をつくる設計、事故を防ぐ設計──その感覚は、運行管理者の知識を得たからこそ、持てた視点でした。
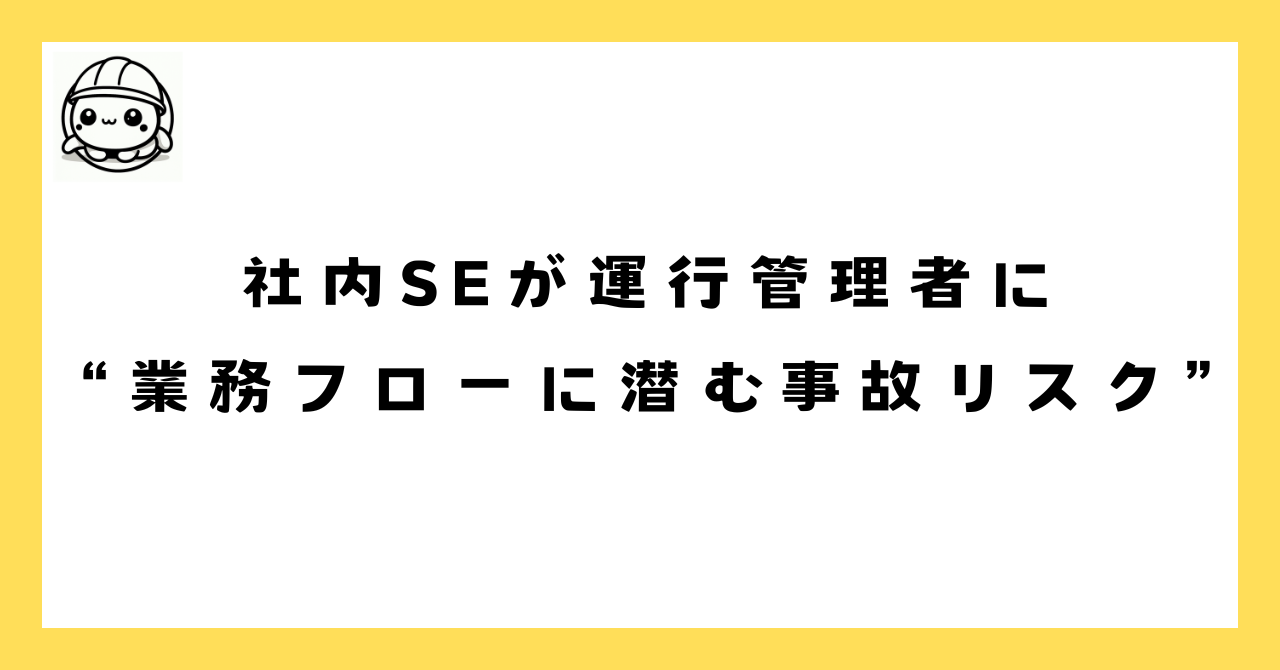
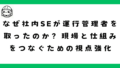
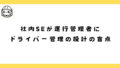
コメント