はじめに
医薬品物流の現場では、単に“運ぶ”だけではなく、温度・ロット・期限・トレーサビリティといった複雑な条件を満たす必要があります。特に3PL(サードパーティ・ロジスティクス)として委託される立場では、製薬会社や薬局チェーンが要求する水準を確実に満たしながら、コストや作業効率も考慮しなければなりません。
この記事では、社内SEとして私が医薬品3PL現場に関わった経験をもとに、医薬品特有の物流要件とそれに対応する情報システムの実装について、温度管理・ロットトレース・入出庫の記録方法などの観点からお伝えします。

医薬品の世界って、まさに「正確さ」が命。SEも責任重大…でも、やりがいもひときわです😊
温度管理:ゾーン別+実績記録
医薬品の保管は、常温(15~25℃)、冷蔵(2~8℃)、冷凍(-20℃)などゾーンごとに明確な管理が必要です。倉庫内はゾーンに分かれ、入荷時から出荷時まで、どのゾーンにいたかを記録する必要があります。
温度はロガーで常時記録され、異常があればアラートが飛ぶ仕組みに。社内SEとしては、温度データをロットや入荷実績と紐づけて保存し、将来のトレーサビリティやクレーム対応に備えるシステム設計が求められます。
ロット管理とトレーサビリティ
「誰に、いつ、どのロットの医薬品を渡したか」が明確にわかること──それがトレーサビリティの基本です。在庫はロット単位で管理し、出荷時もFEFO(先入先出し)または期限順出荷が徹底されます。
SEとしては、ロット情報と期限を持った在庫構造を用意し、入荷・出荷・移動・廃棄すべてのログを自動記録する設計にすることで、現場に負担なくトレース性を高めることができます。
医薬品ならではのトラブルと対処
一度、冷蔵ゾーンに入るはずの製品が常温側に誤って格納され、期限超過で廃棄処理になったことがありました。このとき、スキャンログと棚番号の移動履歴がすべて残っていたため、原因と責任の所在を明確化することができ、改善策(ダブルチェックとゾーン警告アラート)も迅速に導入できました。
このように、トラブルを未然に防ぐだけでなく「起きた後に立証できる」仕組みがあるかどうかが、医薬品物流の信用に直結します。SEの設計が“品質保証”の一翼を担っているという意識が必要です。
まとめ:医薬品物流を支えるSEの責任
医薬品3PLは、「止められない」「間違えられない」業務の連続です。現場の努力だけでは成り立たず、システムによる管理・検証・記録が不可欠です。そしてその構造をつくるのが、私たち社内SEです。
温度、ロット、期限、履歴。どれか一つでも欠けると、命に関わる分野だけに信頼は崩れます。逆に言えば、きちんと仕組みに落とし込めれば、大きな信頼を得ることができます。私はこの現場で「システムが信用の土台になりうる」ことを実感しました。
さらに、法規制(GDP、GMPなど)への対応もSEの設計に関わる重要な要素です。現場は法令に即した運用を求められ、帳票や履歴の保存ルール、温度逸脱時の対応ルールもあらかじめシステムで担保されている必要があります。
「ヒューマンエラーを完全になくすことはできない」。だからこそSEは、エラーの発生を前提にした“検知と復旧”の仕組みを備え、現場が安心して業務に専念できる環境をつくる必要があります。見えないところで現場を守るのもSEの仕事です。
そしてもうひとつ重要なのが、SE自身が現場の緊張感と責任の重さを共有する姿勢です。単なるシステム提供者ではなく、「共に医薬品を守っている」当事者としての意識が、結果的により良い設計につながっていくのだと思います。

「命をつなぐ物流」を支える設計って、ほんとにすごい仕事ですよね。SEの責任、じわっと感じます😊
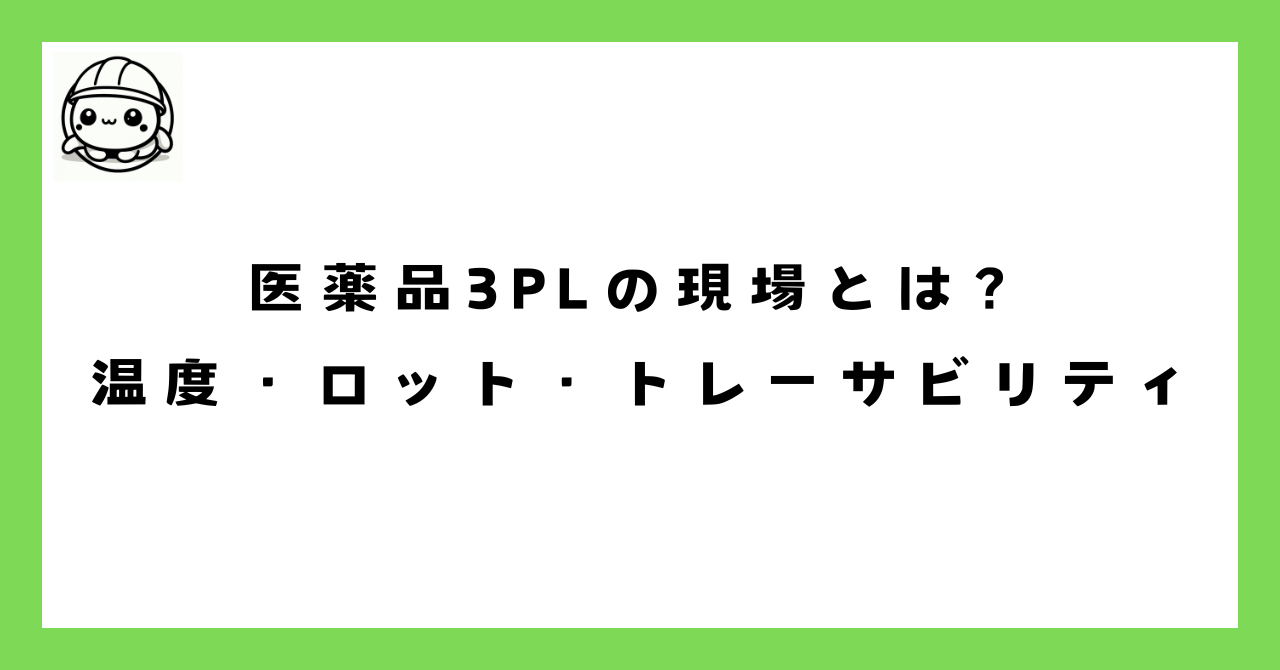
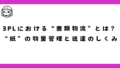
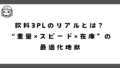
コメント