はじめに
「この作業は○○さんじゃないとできない」「引き継ぎ資料を作ろうにも、何をどう説明すればいいか分からない」──そんな状況に心当たりはありませんか?それこそが“属人化”の正体です。業務が人にひもづいてしまっていて、仕組みとして捉えられていない状態。社内SEとして私が最も頭を抱えたのも、この属人化された現場の整理でした。
この記事では、属人化とはそもそも何か、なぜ問題なのか、そして実際にどのように構造化・文書化・可視化していったかを、私の実体験に基づいてご紹介します。技術やツール以前に必要な“見方の変換”が、属人化をほどいていく第一歩になります。

属人化が進むと、やる人が休んだだけで詰むんですよね…。地道でも、見える化ってほんと大事です!😊
属人化の構造とそのサイン
属人化には段階があります。最初は「手が早い人に頼る」、そのうち「その人しか分からない業務ができる」、最後には「やってる本人も手順を整理していない」状態に。こうなると、業務のブラックボックス化が起こり、異動も育成も機能しなくなります。
属人化のサインは「説明できない作業」「手順書があっても使えない」「教えるときに“慣れれば分かる”が出る」などです。これらを無視していると、業務継続リスクが高まるだけでなく、他者に任せることが難しいままになります。
まずは“棚卸し”と“単位分け”から
私が現場に入ったとき、最初に行ったのは業務棚卸しです。個人が何を、どの頻度で、どの順で、どのシステムを使ってやっているのかをすべて書き出し、共通点・分岐点・属人ポイントを洗い出しました。
そして、業務を「1業務=1単位」として再編成。複数の作業が混ざったままの状態では伝承も難しいため、単位分けによって「これは誰にでも引き継げる」「これは設計の見直しが必要」という判断ができるようになります。
手順書ではなく“シナリオ”を作る
属人化対策でよくある「マニュアルを作りましょう」は、効果が限定的です。大事なのは、単なる操作手順ではなく、「なぜこの処理をするのか」「どこに注意点があるのか」という“業務シナリオ”の共有です。
私は手順書をストーリー形式にして、背景・目的・例外パターンまで記載しました。「トリガー→処理→結果→次の工程」という流れを、業務フロー図や動画マニュアルとあわせて作成することで、理解が深まりやすくなりました。
まとめ:属人化は“構造化”でほどける
属人化をなくすとは、「誰でもできる」状態をつくることではなく、「再現可能な構造にする」こと。人の能力に頼るのではなく、業務を仕組みとして記述し、誰がやっても一定の品質で実行できるようにする。それが社内SEに求められる役割です。
そして、構造化された業務は、引き継ぎだけでなく業務改善・自動化・外注判断など、すべての判断の基盤になります。つまり、属人化の解消は終わりではなく、現場の進化の始まりなのです。
特に中小規模の現場では、「この人がいないと動かない」状態を解消するだけでなく、「業務の本質を言語化する」ことがチーム全体の学びにもつながります。見える化と対話を通して、現場の属人知が形式知へと転換されていくプロセスこそ、SEの介在価値といえるでしょう。
属人化を恐れるのではなく、「属人知を拾い上げて翻訳する」ことで、次の誰かにつなげる土台をつくる。そうした“構造の架け橋”を築くのが、現代の社内SEの仕事だと私は考えています。

引き継ぎって「気合い」じゃなくて「構造」なんですよね…!整理すればするほど、道が見えてきます😊
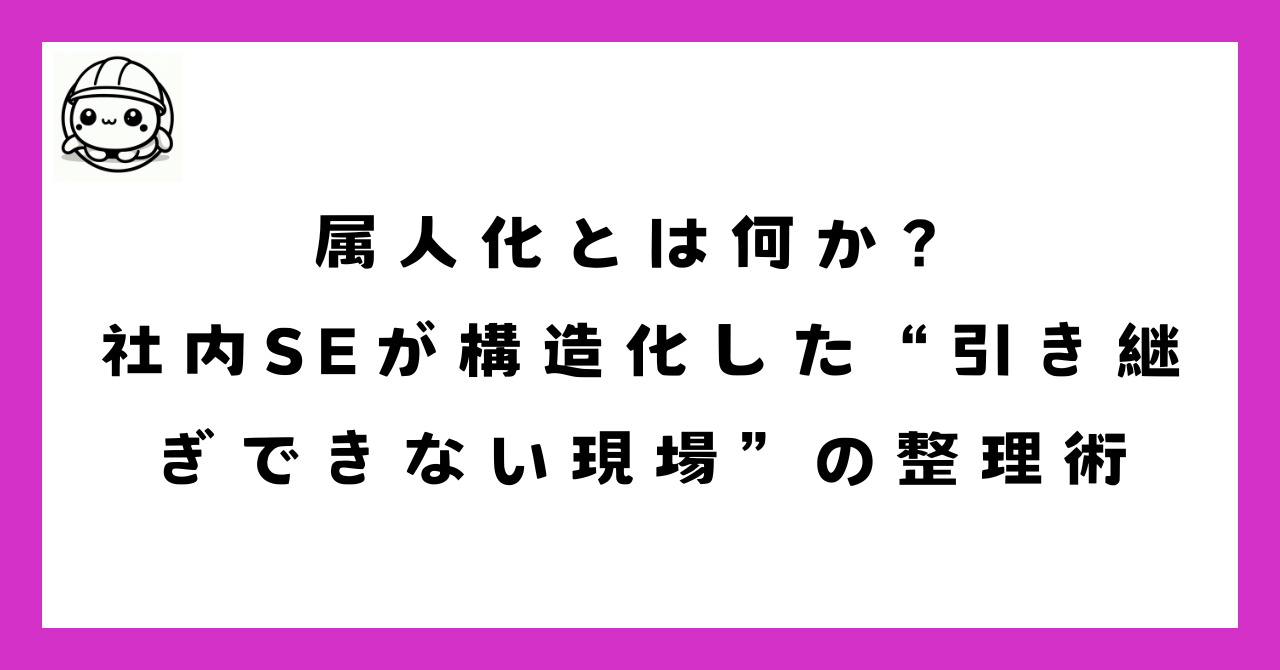
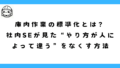
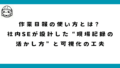
コメント