はじめに
「A倉庫には在庫が余ってるのに、B倉庫は欠品寸前」──拠点をまたぐ物流の世界では、このような“在庫の偏在”がよく起こります。そして、ここに対応するのが「拠点間移動」という手段です。
しかし、単に「在庫を移す」だけでは済まないのが現実です。移動のトリガー、在庫帳簿の一致、移動中ステータスの扱い、現場の受け入れ準備──すべてが連携していなければ、混乱と誤差が発生します。
この記事では、社内SEとして拠点間移動の仕組みを整備した筆者が、システム面・現場面の両方から見た課題と設計の工夫を、実例を交えて解説します。

在庫があるのに欠品する──って、もったいないですよね。つなぐ仕組み、すごく大事なんです😊
事例①:帳簿在庫は移ったのに、現場では“届いてない”
以前の現場では、WMS(倉庫管理システム)上では“拠点間移動済”と表示されていても、実際の現場には商品が届いていないという事例が発生していました。原因は、「出荷登録=移動完了」とみなしていたこと。
出荷担当は処理後すぐに“完了”にし、移動中在庫として区分されないまま帳簿上はB倉庫へ移っていました。結果、B倉庫は“あるはずの在庫が来ない”と現場混乱。
この課題を受け、私は「中継在庫」状態を新設し、「出荷済→移動中→入荷済」までをステータスで管理できるよう、システムを改修しました。
事例②:拠点間で“品番呼称”が違う問題
拠点ごとに管理番号の運用が異なっていた例もありました。A拠点では「商品コード+色記号」で管理していたのに対し、B拠点は「品名記号+枝番」。同じ商品なのに、移動時に突合ができないという状況が発生しました。
このような品番の“非統一”は、データベースを統合していない組織ではよくある問題です。私はこれに対し、「マスターコード変換テーブル」を設け、移動元・移動先での品番を自動変換する仕組みを導入。WMS間の連携に成功しました。
情報の壁:拠点間で“前提知識”が違う
拠点間連携で最大の壁は、「同じ会社でも文化が違う」ことです。A拠点では朝一で入荷を待つ文化があるのに、B拠点では午後まとめて処理するなど、オペレーションの流れ自体が異なります。
これにより「こっちはすぐ出したのに、そっちはなぜまだ?」という摩擦が起きがち。私は、Slackと連動した「移動ログ通知Bot」を構築し、出荷・到着・処理までを見える化。情報の非対称性を減らす工夫をしました。
まとめ:拠点間移動とは“連携の設計”である
拠点間移動とは、ただの在庫移動ではなく、「異なる拠点がひとつの組織として連携する」ための仕組みです。そのためには、情報の粒度、タイミング、呼び方、在庫状態──すべてを合わせて“動線”として設計し直す必要があります。
社内SEとして大切なのは、データが移ることだけでなく、「人が混乱せずに扱える」ようにすること。帳簿・現場・感覚が揃って初めて、拠点間移動は“効率化”として機能します。
そして忘れてはならないのが、“曖昧なままにしないこと”。現場のルール・命名・処理タイミングがバラバラなら、どんなに良いシステムでもミスを防ぐことはできません。共通言語を作り、工程を揃え、トラブルの芽を未然に摘む。拠点間移動は、そうした“物流の言語統一”でもあるのです。

在庫があるのに足りないって、ほんともったいない!しくみで在庫の“つながり”を作っていきましょう😊
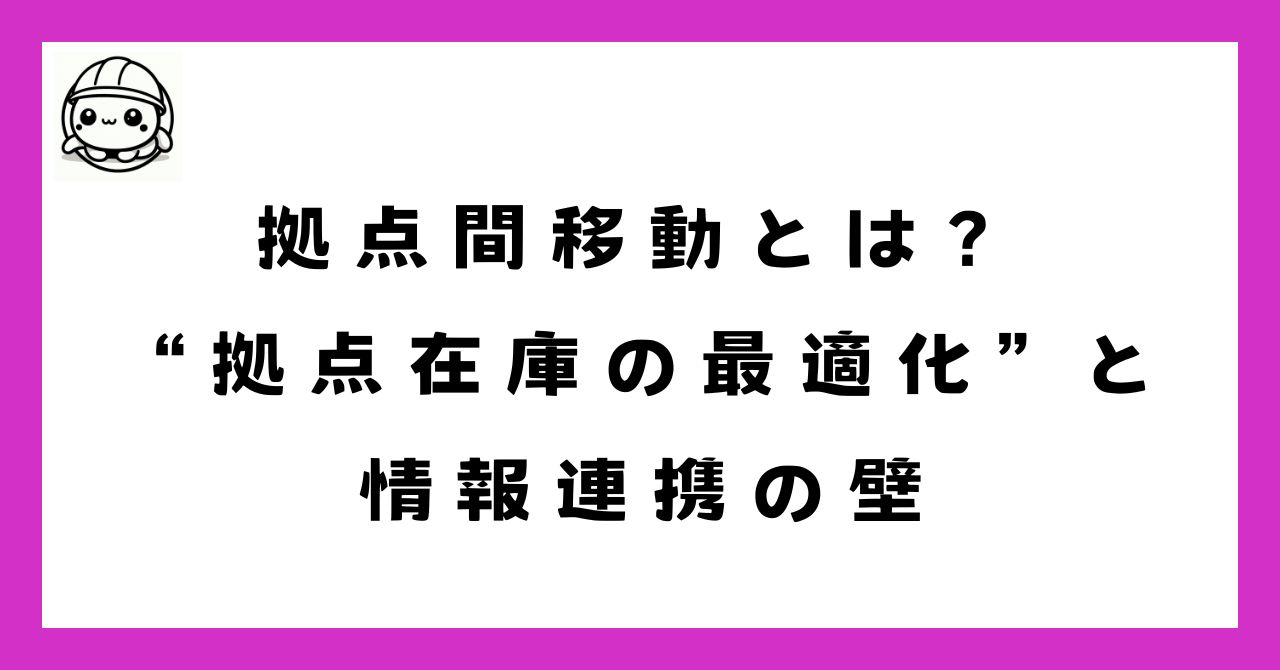
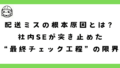
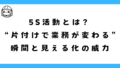
コメント