はじめに
「バーコードを導入すれば効率化できる」──そう思って導入したはずなのに、実際にはスキャンエラーや運用ルールの混乱が頻発してしまう。そんな悩みを抱えている現場は、意外と多いものです。
この記事では、社内SEとして実際に行ったバーコード運用導入の経験をもとに、「ただ読み取れる」だけではない、“運用できる仕組み”の設計術について詳しく紹介します。

バーコードって、導入しただけで終わっちゃうケースも多いんです。でも本番はそこからなんですよ😊
バーコード運用とは?基本の整理
バーコード運用とは、製品・資材・伝票などにバーコード(JAN、QR、CODE128など)を付与し、スキャナなどで読み取ることで、業務情報を正確かつ迅速に取得・処理する仕組みのことです。単なるコードの貼付けではなく、運用設計・ルール化・教育まで含めて初めて「活きたバーコード」になります。
業務の属人性を減らし、作業ミスを防ぐ手段としても注目されており、特に物流・製造・小売・医療などの分野で導入が進んでいます。しかし、「バーコードがあっても読み取れない」「どれをスキャンすればいいのかわからない」といった声が現場から上がるケースも多く、導入と運用のギャップが課題になります。
事例①:バーコードの貼る位置で現場が混乱
ある物流拠点では、製品ラベルにバーコードを付けたにも関わらず、「読み取れない」「時間がかかる」という声が続出していました。原因を調査すると、バーコードの貼付位置がバラバラで、棚に入った状態ではスキャナが届かないケースが多発していたのです。
私は現場スタッフとともに「貼付位置ガイドライン」を作成し、各製品に統一ルールを設けました。また、棚のスキャン口に照明を追加し、読み取り効率も改善。結果として、誤読が激減し、ピッキング作業の平均時間が15%短縮されました。
事例②:バーコードが多すぎて、逆に選べない
別の現場では、1つの箱に複数のバーコードが印刷されており、「どれをスキャンすればいいのかわからない」というトラブルが日常的に発生していました。現場作業者の判断に任せたことで、誤スキャンや二重登録が多発していたのです。
この問題に対し、私は「有効バーコード」だけに赤枠・マーカーを追加し、スキャン対象を明確化。さらに読み取り時にコード種別を自動判定し、フォーマットが異なる場合はアラートが出るよう設定しました。その結果、誤処理件数が月150件から20件にまで激減しました。
事例③:「読み取り後の動き」が設計されていなかった
ある工場では、製品ラベルのバーコードを読み取っても、その後のシステム処理が手動入力のままで、実は「何も効率化されていない」というケースもありました。これは「読み取ること」が目的になり、「読み取ったあと」が設計されていなかった典型例です。
この課題を受け、スキャンと同時にロット・製造時間・担当者を自動記録する仕組みを構築。さらに読み取りログを日報として出力することで、工程管理まで一体化しました。バーコードは、単なる手段ではなく“情報の入口”として機能し始めたのです。
バーコードにも“規格”がある──選定ミスがトラブルの元に
バーコード運用を始める際に意外と見落とされがちなのが、「バーコードの規格(シンボル体系)」です。ひとことでバーコードといっても、実は様々な種類があり、それぞれ用途や読み取り条件が異なるのです。
- JANコード(EAN): 主に商品管理(POS)で使われる13桁または8桁の汎用コード。スーパーやコンビニでおなじみ。
- Code 39: 英数字・一部記号を扱える。読み取りやすく、工業系の現場でもよく使用されるが、文字数が増えるとサイズが大きくなりやすい。
- Code 128: 英数字・記号・制御コードを幅広く表現可能。高密度でサイズが小さく、物流や製造業に最適。
- ITF(Interleaved 2 of 5): 数字のみのコードで、段ボールなどの外装表示用。スキャナ性能に左右されやすい。
- QRコード: 2次元コード。URLや複数情報を含められるため、情報量が多い場面に向く。スマホ読み取りも可。
- DataMatrix: QRコードよりもさらに小さいスペースに大量の情報を記録可能。医療や電子部品でよく使われる。
たとえば、「Code 128で作ったつもりが、実はCode 39で出力されていた」など、フォントや印刷ソフトの設定ミスでトラブルになるケースもあります。また、スキャナが対応していない規格を印刷してしまうと、読み取り不能になる危険も。
そのため、バーコードを導入する際は次の点に注意することが大切です:
- 使用するスキャナが対応している規格を事前に確認する
- 利用目的(商品管理、工程管理、トレーサビリティなど)に合った規格を選ぶ
- 印刷サイズと解像度(dpi)にも配慮し、つぶれや読み取りエラーを防ぐ
バーコードは“記号”であると同時に、“通信インターフェース”でもあります。だからこそ、運用設計とあわせて、規格の選定は慎重に行いましょう。
まとめ:バーコードは「読み取れる仕組み」まで設計してこそ
バーコード運用は、印刷して貼るだけでは意味がありません。どこに貼るのか、どう読むのか、読んだ情報はどこに流すのか。そうした一連の流れが“仕組み”として組み込まれて初めて、業務改善として成果が現れます。
社内SEとしては、バーコードという技術を使うだけでなく、それを「どう活かすか」にまで踏み込む必要があります。貼付ルール、読取対象の選定、スキャン後の処理──それらはすべて、業務とシステムの橋渡し役として設計すべき領域です。
現場にとって「スキャンすれば終わる」状態が理想です。そのためには、読み取り精度・作業動線・画面UI、さらには教育や習慣づけも含めて運用全体を設計する力が求められます。読み取りの手間を減らすことが、そのまま現場の安心感や効率に直結するのです。
最終的なゴールは、「誰でも正しく使える」仕組みづくり。バーコードは魔法の道具ではありませんが、“正しく使えば魔法のように効く”ツールです。社内SEの腕の見せ所は、その魔法が毎日安定して使われる環境をつくることにあります。

貼って終わり、じゃない。“読み取れる工夫”があって初めて、現場に活きるんです📦📲
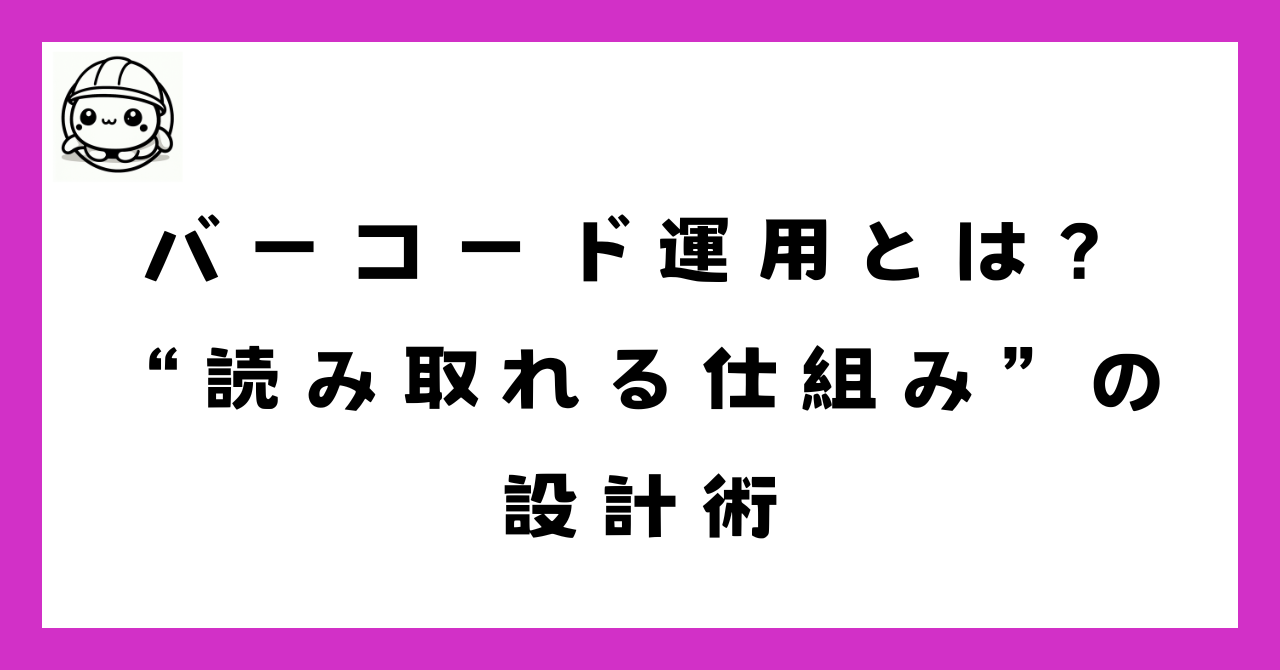
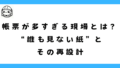
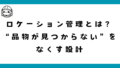
コメント