はじめに
どれだけ丁寧なマニュアルを作っても、「現場では読まれない」「いつの間にか誰も使わなくなる」──そんな経験をされた方も多いのではないでしょうか。
マニュアルが定着しない理由は単純ではなく、往々にして“教育”と“実運用”の間にあるズレが原因です。この記事では、社内SEとして複数の現場を支援した中で実感した「マニュアルが使われない構造的な理由」と、その改善策を実例を交えて解説します。

「マニュアル通りにやればいい」って言うけど、そもそも読まれてなかったら意味ないんですよね…😊
事例①:「覚えた方が早い」という空気
ある倉庫現場では、マニュアルが配布されているにもかかわらず、新人がベテランに口頭で作業を教わっていました。理由は単純で、「いちいち読むより、人に聞いた方が早い」から。
この状態では、作業のやり方が人ごとに違い、誤差やトラブルも多発。「誰が教えたか」が品質に直結しており、教育も属人化していました。
私はこの現場に、5分で読める「初動マニュアル」と、1分動画のQRコード付きフローを導入。教育係も一緒に見ることで、「教える側のばらつき」を減らし、作業の統一をはかりました。
事例②:マニュアルが更新されない
別の現場では、作業内容が少しずつ変わっているのに、マニュアルは5年前のまま。新しく入った人は「どれが正しいの?」と混乱し、結局ベテランの言うことに従うという悪循環に。
私はこの現場に、「更新履歴が残るGoogleスライド形式のマニュアル」を導入。誰がいつどの内容を変えたかを可視化し、現場のリーダーが定期的にレビューするルールを設けました。
これにより「現場とマニュアルの不一致」が解消され、「文書が古くなるから使われない」状態から脱却できました。
まとめ:マニュアルは“現場と一緒に育てる”もの
定着しないマニュアルには共通点があります。それは、現場で使うために作られていないこと。上からの指示で形式的に作成され、運用とのズレを放置したままでは、どれだけデザインや文言を工夫しても活用されません。
社内SEとして感じるのは、「マニュアル=完成形」ではなく、「マニュアル=対話のきっかけ・共有のハブ」と捉える視点が重要だということです。
作成後も、現場からのフィードバックを受けて更新し続ける。教える人・教わる人の両者が共通の“参照点”として扱えるようにする。その循環ができて初めて、「マニュアルが運用に定着する」と言えるのではないでしょうか。

“マニュアルあるのに使われない”…って、本当に多いんです。でも、それって仕組みの責任かもしれません😊
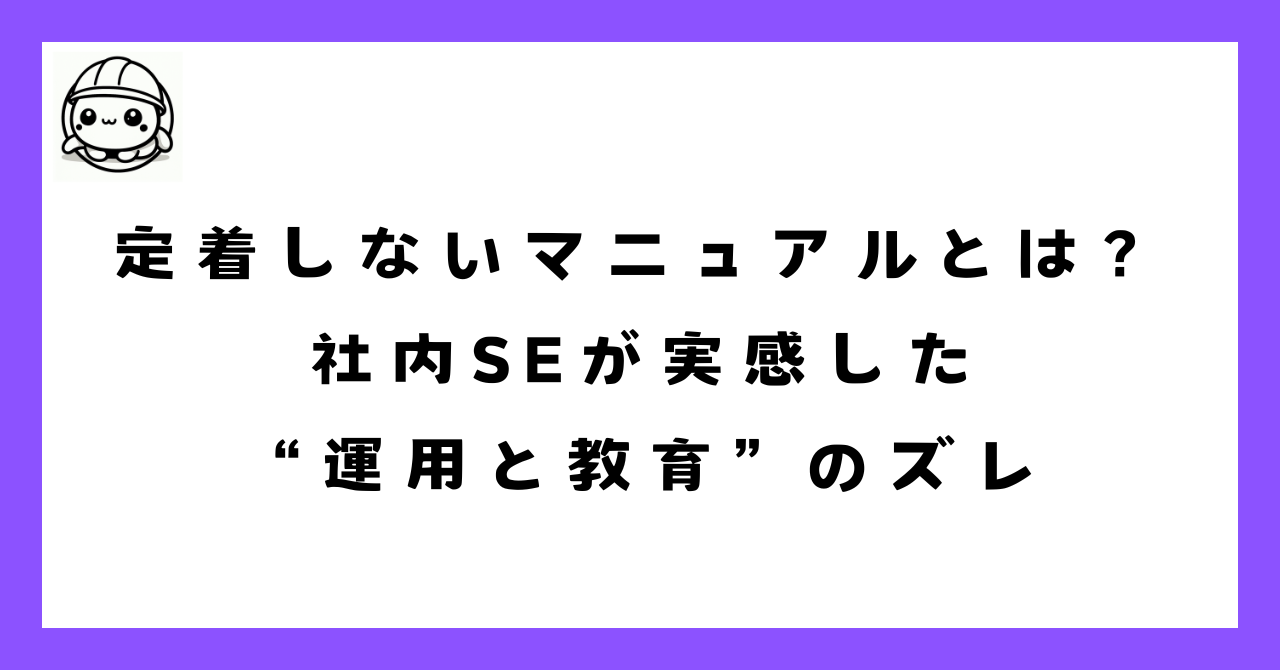
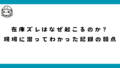
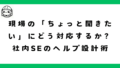
コメント