はじめに
物流現場で起きる“あるある”──たとえば「またラベルが剥がれてた」「誰かが帳票を机に置きっぱなし」「午後になると誰もチェックしていない棚が出てくる」。こうした一見ささいな出来事が、じつは大きな業務リスクや非効率の原因になっていることがあります。
社内SEとして現場に入る中で、私はこれらの“あるある”を「仕方ない」と流すのではなく、「仕組みに変えられないか?」という視点で見つめなおしてきました。この記事では、私が実践してきた“現場のあるある”を“仕組み”に変えるプロセスとその工夫を、いくつかの事例をもとにご紹介します。

「あるある」で済ませず、「なんとかできないかな?」って考えるのがSEの出番ですね😊
事例①:放置されがちな帳票 → デジタル受領確認の導入
「伝票、どこ行った?」──これは定番の現場あるあるです。紙の帳票が一時置きされたまま誰の手にも渡らず、確認漏れや二重チェックの原因になります。
この問題に対し、私は「帳票にサインをする」工程を廃止し、スマートフォンによるQR読取+確認ボタンの仕組みを作成。帳票番号を読み込んでチェックした日時と担当者をGoogle スプレッドシートに記録できるようにしました。
これにより、確認漏れはゼロに。さらに「誰がいつ確認したか」が一目で見えることで、責任の所在も曖昧にならず、トラブルも激減しました。
事例②:「声かけ忘れ」 → アラートつきチェックリスト
物流の現場では、「〇〇終わったら声かけて」がよくあります。しかし声かけは忘れられがちで、次工程が止まる、急な呼び出しでバタつく──これも日常的な“あるある”でした。
私はGoogleフォームとLINE通知を組み合わせ、作業完了報告をフォームで送信→登録先にLINEでアラートが届くシステムを構築。個人名入り・工程名入りで届くため、見逃しや責任のなすりつけもなくなりました。
シンプルな仕組みですが、「誰かに依存しない」ことが非常に大きな価値を生みました。
事例③:ピッキング順が毎回バラバラ → ロケ順自動整列
作業者が持つリストが、毎回商品の並び順にバラバラで「探すのに時間がかかる」という課題もありました。ここには“システム上の商品並び”と“倉庫のロケ順”のズレという構造的な問題が隠れていました。
そこで私は、商品リストを倉庫のロケーション順に並び替える自動処理をGASで作成。フォームで日付を選ぶと、その日の出荷商品がロケ順で一覧化されるようにし、印刷用PDFも自動出力されるようにしました。
「歩数が減った」「新人でも迷わなくなった」と高評価を得られ、標準業務へ定着させることができました。
まとめ:「あるある」は仕組み化の宝庫
現場の“あるある”は、実は課題の原石です。それをSEの目線で抽出し、仕組みに変えることで、再発を防ぎ、教育の標準化にもつながります。
仕組み化とは、現場で起きる「よくあること」を、「誰がやっても同じ結果になるように設計すること」。地味な繰り返しですが、その一つ一つが現場の安心と余裕を生みます。
「いつも誰かがやってくれてる」「今日もたまたま回った」──その不安定さを“しくみ”でなくしていく。現場に寄り添うSEの腕の見せ所です。
また、“あるある”という言葉の裏には、現場の無力感やあきらめが隠れていることもあります。「またか」「どうせ変わらない」──そうした思考停止を打破するには、小さな成功体験の積み重ねが不可欠です。「ここ変わったね」「便利になったね」と感じられる工夫が、現場に前向きな変化をもたらします。
私自身、仕組み化という取り組みの中で何度も失敗しましたが、現場の反応を見て修正を重ねることで、少しずつ“信頼”が積み重なっていきました。「提案すれば何か変えてくれるかも」──そう思ってもらえるようになってから、改善の連鎖は加速しました。
つまり、仕組み化とは単なるツール導入や自動化ではなく、現場の空気・文化・心理にも働きかける、ひとつの対話のかたちなのです。
そして忘れてはならないのが、“あるある”の背景にある人の行動や感情です。「つい置きっぱなしにしちゃう」「気づいたけど言い出せなかった」──そうした現場の“リアル”に耳を傾け、仕組みにやさしさを込めることが、持続可能な改善につながります。
仕組み化の本質は、課題を「気づける化」し、改善を「共有できる化」し、解決を「忘れず続けられる化」すること。そんな三段階の仕組みを意識することで、現場に定着する改善が生まれます。

ちょっとの仕掛けで現場が笑顔になる。そんな仕組みを、これからも作っていきたいです😊
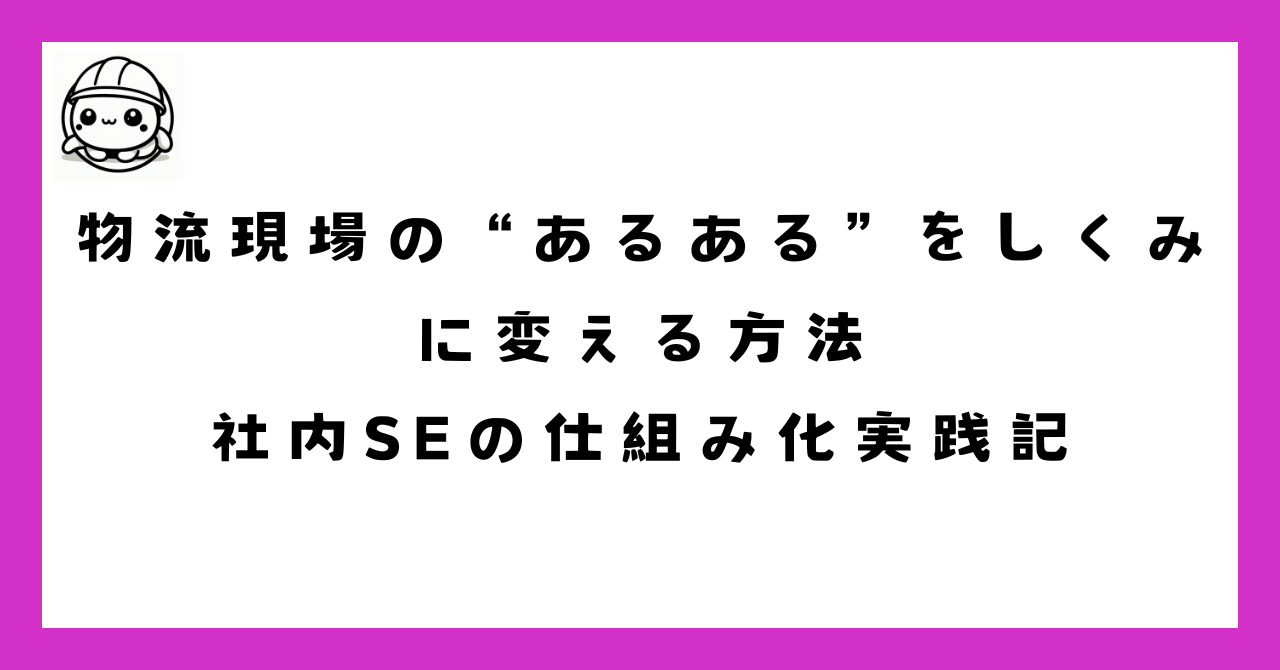
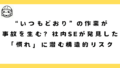
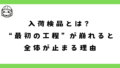
コメント