はじめに
3PL(サードパーティ・ロジスティクス)として、企業や団体から「書類の保管業務」を委託されるケースは少なくありません。紙書類は温度管理や消費期限が不要な分、手間が少ないと思われがちですが、実際には“設計次第で大きく品質と効率が変わる”分野です。
本記事では、社内SEとして公的機関の資料保管業務に携わった経験をもとに、3PLが書類保管を請け負う際に押さえるべき利点と注意点、そしてシステム設計の実例についてご紹介します。

「紙の保管なら楽でしょ?」って思ってたんです。でも、ミスが起きるのって、いつも“紙”なんですよね😊
紙書類保管のメリット
書類の保管は、温度・湿度・鮮度といった環境要因に左右されにくく、以下の点でメリットがあります:
- 消費期限がない:食品や医薬品と違い、長期保管が可能
- 温度管理が不要:常温倉庫で対応でき、設備コストが低い
- 棚管理がしやすい:サイズが一定で、箱単位で整理しやすい
これらの特性は3PLにとっても管理しやすく、スタート時点での設備投資が抑えられる利点があります。
設計で気をつけたい“落とし穴”
ただし、書類は「傷まない」一方で「見つからない」「間違える」「戻らない」といった“人的ミス”が起きやすい特徴もあります。
- 検索性の低さ:ラベルが曖昧だと、目的の書類が見つからない
- 誤保管の多発:似た番号や書式で混同しやすい
- 属人化リスク:台帳や記憶で管理していると、担当者以外が対応できない
「紙なら安心」と思われがちですが、実は“管理があいまいになりやすい”という側面があり、棚配置・管理番号・台帳記録などの標準化が不可欠です。
実例:公的機関の書類保管システム化
ある自治体から、段ボール1,000箱分の書類保管業務を委託された際の話です。書類は毎月出入りし、出庫・返却の履歴をすべて紙台帳で管理していました。しかし、管理番号の貼り間違いや棚ラベルの劣化で、「資料が見つからない」「誤って出庫した」などのトラブルが相次いでいました。
私はこの業務に、OCR付きスキャナーとWebベースの入出庫管理システムを導入。箱に貼られたバーコードを読み取り、画面上で履歴照会・返却期限管理・保管位置の検索ができるよう再設計しました。さらに、仮置き中と正式保管を分けて管理することで、「いま戻ってきたが棚が空いていない」といった混乱も防げるようになりました。
書類そのものはシンプルでも、出し入れの履歴・責任者・目的などが紐づくことで業務の複雑さは一気に増します。その情報を「探さなくていい形」に整えるのが、SEとしての役割だと感じました。
まとめ:紙でも“物流”である以上、しくみで支える
紙の保管は、“簡単そうで実は奥が深い”領域です。保管そのものは難しくなくても、「探す」「返す」「間違えない」という運用においては、システム的な支援が求められます。
とくに委託業務として請け負う場合、顧客から求められるのは「安心して預けられる体制があるか」という点です。紙だからこそ、手作業で管理できてしまう領域が残りやすく、だからこそ属人化や運用のあいまいさがリスクになります。
管理番号の一元化、履歴管理、仮置きと正式棚入れの区別、帳票レスな追跡手段の用意など、小さな工夫の積み重ねが「再現性のある管理体制」へとつながります。それはそのまま、現場での作業品質と、顧客の信頼確保に直結します。
また、紙の保管が長期化すればするほど、「誰が見ても分かる状態であること」が重要になります。5年後・10年後に誰かが引き継ぐことを想定した運用ルールを設計し、最小限の操作で最大限の情報が得られる仕組みを整備する。それが、紙書類の“持続可能な物流”です。
3PLが担う書類保管は、単なる箱の管理ではなく、情報の信頼性を守る業務でもあります。紙であっても、SEの技術と視点で整えられることは多くあります。今ある紙にどこまで工夫を施せるか──その一手が、業務全体を支える基盤になるはずです。

「壊れないけど、なくなりやすい」──それが紙の難しさ。でも、そこを仕組みで守っていくのがSEの腕の見せどころですね😊
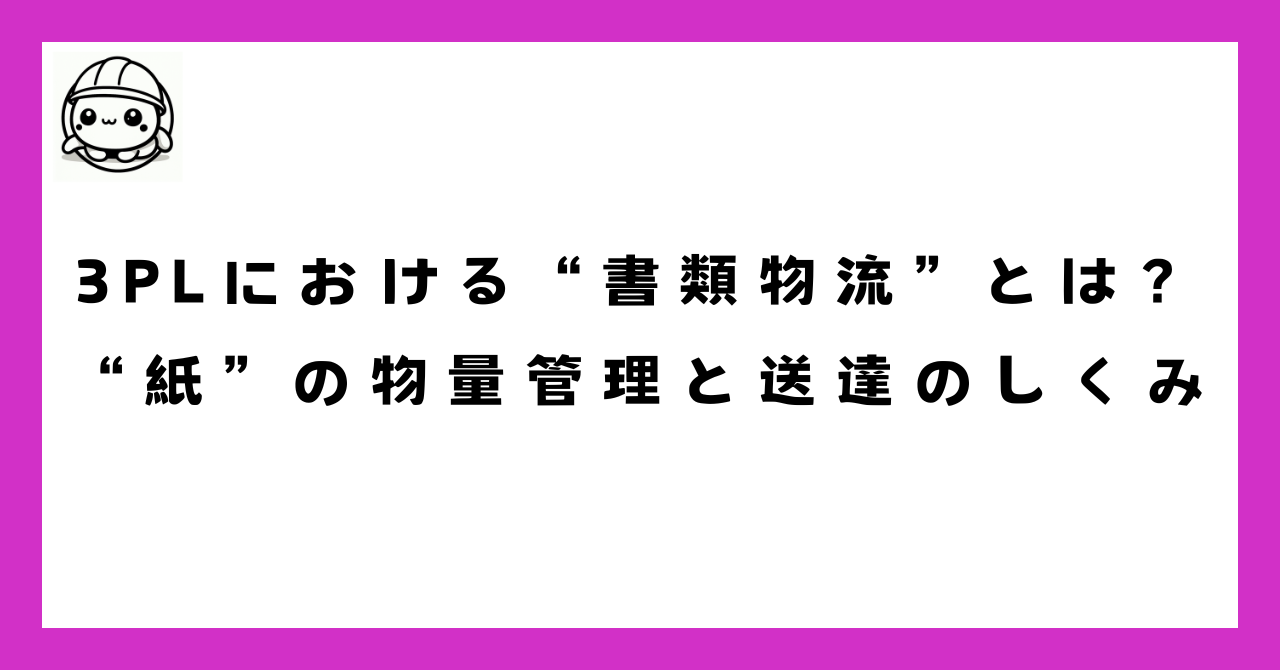
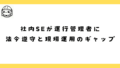
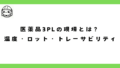
コメント