はじめに
運行管理者の資格を取得し、初めて真剣に向き合った「法令」と「現場」のギャップ。その違和感は想像以上でした。法律では“こうしなければならない”と明記されていても、現場では“できない”あるいは“やっていない”という場面があまりに多かったのです。
この記事では、社内SEとして現場の業務設計を行ってきた私が、運行管理者資格を通じて気づいた「法令遵守の理想」と「運用の現実」とのズレ、そしてそれを埋めるためにシステム担当者が果たせる役割について詳しく掘り下げます。

資格を取ると“べき論”が見えてくる。でも現場には“できない理由”がある──このギャップ、本当に大きいです…😅
“理想の点呼”と“実際の点呼”
法令上、運行前後の点呼は必須です。対面またはIT点呼により、健康状態・アルコールチェック・免許証確認を実施しなければなりません。しかし、実際の現場では「運転者がすでに出てしまっている」「そもそも点呼記録を残せていない」という例も珍しくありません。
とくに朝の出庫ラッシュ時は、点呼者が足りず形式的な確認になりがちです。現場は「事故が起きていないから大丈夫」と考えがちですが、法令の観点から見れば明確な違反。ここに大きな断絶があります。
拘束時間の“管理されていない現実”
運行管理者試験では、「1日の拘束時間は原則13時間、延長しても15時間、週あたり2回まで」と学びます。しかし、実際の配車では「朝6時に出て、夜21時に戻る」ような拘束時間オーバーが恒常化している現場も存在します。
この要因のひとつが、業務設計に「法令」が組み込まれていないこと。時間管理が“労務”ではなく“現場の慣習”に任されてしまっているのです。システム上の時間記録やアラートが機能していれば、防げたはずの違反が日常化している例もありました。
“安全ルール”の形骸化を止めるには
たとえば「4時間以上運転したら30分休憩を取る」。このルールも実際には「到着後に休んだことにする」などの慣習的な“処理”にされてしまうケースがあります。本来は運行指示の段階で「休憩ポイントを設ける」べきなのに、現場任せになっているのです。
このような形骸化を防ぐには、「設計にルールを埋め込む」ことが重要です。ルート作成ツールに休憩挿入の自動提案を設ける、ドライバーアプリにリマインダー機能をつける──仕組みの工夫で“守りやすい設計”に変えていく必要があります。
まとめ:SEは“解釈と翻訳”の架け橋
法令は「こうすべき」で動き、現場は「こうするしかない」で動く。その間に立つSEが果たすべき役割は、“翻訳者”であることだと私は思います。どちらか一方の論理だけで物事を進めると、ギャップは広がるばかりです。
資格を取ったことで、理想を知った。でも現場にいるから、現実も知っている。その2つをつなげる視点こそが、これからの社内SEには求められているのではないでしょうか。
「それ、ルール的にアウトです」ではなく、「その動きなら、こうすれば守れますよ」と提案できるように──システムは“違反を責めるため”でなく、“守れるように寄り添うため”に使う。その発想転換が、真の業務改善につながるはずです。
加えて、業務システムに「法令を反映する」ことは、単なる法務対応ではなく、従業員を守ることにつながります。休憩の挿入、拘束時間の制限、点呼の記録──これらを“抜け”のないように設計し、かつ現場で使いやすく整えるのがSEの腕の見せどころです。
社内SEが運行管理の知識を持つというのは、言わば「現場の言語」と「法律の言語」を理解したうえで、業務全体の安全性と実効性を高める通訳になること。そんなポジションを担うSEが一人でも増えることで、日本の物流はもっと強くなる──本気でそう思っています。

ルールって、「守る」だけじゃなく「守れるようにする」ことも大事なんですね。SEって、やっぱり橋渡しの仕事です😊
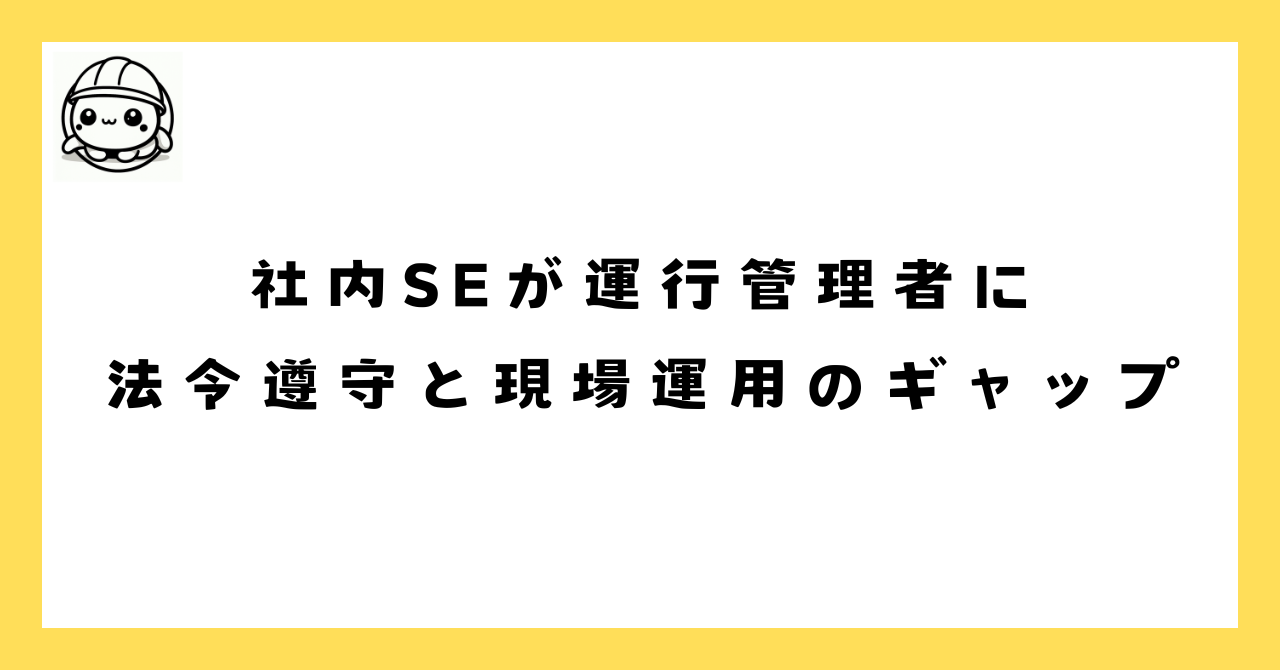
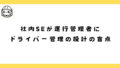
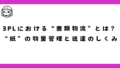
コメント