はじめに
ドライバーの労務管理や運行計画は、運行管理者の仕事。しかし、社内SEの立場から見ると「情報の設計」そのものにこそ、大きな盲点があると気づかされました。データはあるのに伝わらない。記録はあるのに活かされない──そんな“情報の空白地帯”が、日々の業務のなかに存在しています。
この記事では、運行管理者資格を取得した社内SEの視点から、ドライバー管理における情報設計の盲点と、それをどう改善すべきかを具体的に解説します。

「報告したはず」「聞いてない」「管理してるつもり」──そのズレが積み重なる前に、見直せる設計にしたいですね😊
紙か、Excelか、それとも空白か
点呼簿、日報、アルコールチェック、運転記録。これらの情報がバラバラに紙やExcelで管理されている──これは現場では珍しくない光景です。中には「記録しているだけで、誰も見返していない」ファイルもあります。
つまり、“記録”はあっても“設計”されていないのです。情報の流れが可視化されず、データの活用ができないまま放置されている。これは大きな情報損失であり、管理ミスや事故報告の遅れにつながる盲点です。
属人化の壁:「◯◯さんだけが知っている」
「あのドライバーは最近疲れが溜まっている」「あのルートは遅れがち」──そういった現場のナレッジは、ベテラン運行管理者や事務員の“感覚”に頼られていることが多く、データ化されていないこともしばしばです。
この属人化は、体制変更や休職、退職のタイミングで一気に崩れます。「誰も引き継げない」「データはあるが解釈できない」。そうなる前に、SEとして「情報を誰でも扱える構造」にしておくべきです。
“見える化”の第一歩は“紐づけ”から
たとえば、点呼記録と運転ルート、出退勤時刻、事故ヒヤリ情報をすべて「ドライバーID」でひもづける。それだけで「この人の稼働パターンには無理がある」「深夜明け→午前運転が続いている」といったリスク傾向が見えてきます。
つまり、SEに求められるのは“入力フォームの整備”ではなく“データ構造の設計”です。どの情報をどう蓄積するか、どう紐づけるか、どう一覧で見せるか。設計力が、安全管理の精度を大きく左右します。
まとめ:ドライバー管理は“仕組み”で守る
運行管理の現場では、日々多くの情報が飛び交っていますが、それが“管理”されているとは限りません。社内SEが果たすべき役割は、ドライバー管理を「紙やExcelの整理」ではなく「業務の中で回る情報設計」に昇華させることです。
情報は、整理されなければ役に立ちません。記録ではなく設計、感覚ではなく構造。事故を防ぎ、働く人を守るために、情報の設計はシステム部門が担うべき“安全の基盤”なのです。
また、現場が安心して使えるツールであること、誰か一人が抜けても回せる構造になっていること──この2点が、継続性と安全性の両立において非常に重要です。「わかる人しか使えないシステム」は、いざというときに機能しません。
情報設計の肝は、「伝えるべきことが、確実に届くかどうか」。点呼簿、ヒヤリハット、アルコールチェック、日報など、一見ばらばらな帳票群を、意図と構造を持った1つの“仕組み”にすることで、リスクを発見しやすくなります。
社内SEは、単にシステムをつくる人ではなく、情報が流れ、伝わり、守られるための“構造”をデザインする存在であるべきです。ドライバーという「現場の命綱」を、仕組みの力で支える──その意識こそ、現代のSEに求められている役割ではないでしょうか。

設計って奥が深いですね…!人を守る“情報のかたち”を考えるのも、SEの大切な仕事なんだと改めて思いました😊
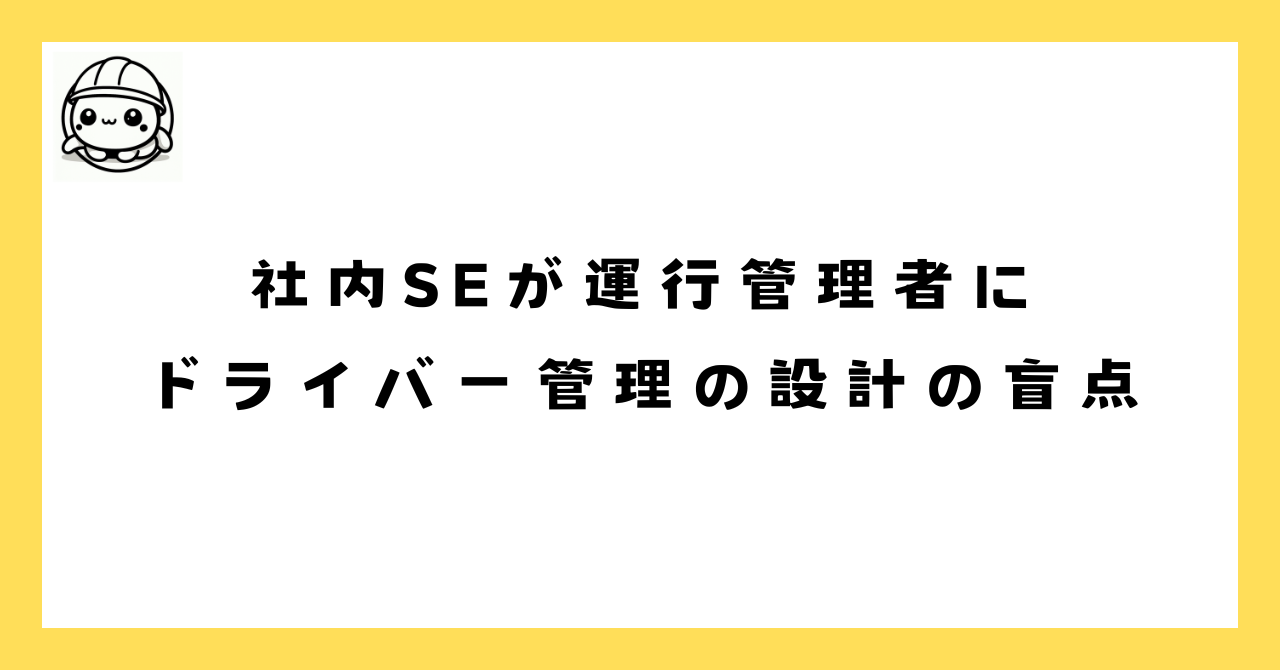
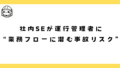
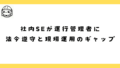
コメント