はじめに
「午前中に注文して、その日の夕方には届く」──当たり前のように受け入れられている当日配送。しかしその裏側では、極めてタイトで、わずかな遅延も許されない物流スケジュールが毎日組まれています。この記事では、社内SEの立場から、当日配送がどのように成り立っているのか、現場で見たリアルな工程と、そこに関わるシステムの要点を紹介します。
単なるトレンドワードとしての「ラストワンマイル」ではなく、注文受付からピッキング、出荷締め、配送車両の出発まで──すべてが「分単位の判断」で成立している当日配送の舞台裏を、SEの目線でひもといていきます。

本当にね、「当日配送って、こんなにギリギリだったの!?」って現場を見て驚きました…!😲
スケジュールは“朝9時”から始まっている
私が担当していた物流センターの多くでは、当日配送対象エリアへの対応が「午前9時の受注データ確定」で始まります。ここで一度、当日配送対象の商品・数量・配送先が確定し、即座にピッキング指示が発行されます。
この9時のタイミングで、前日夜の受注分と当日朝の注文分が混在しており、WMS側でのフィルタリングと波動対応が重要になります。タイムクリティカルなラインを区分けし、優先順序を付けるのもこの段階です。
ピッキングと仕分けは“秒単位の勝負”
当日配送向けのピッキングは、基本的に「トータルピッキング→仕分け方式」が多く採用されています。トータルピックにより作業スピードを最大化し、その後に配送先別に仕分けを行うという流れです。ここでの遅延は出荷全体に響くため、ピッキング指示の最適化と棚配置の最短動線設計がSEの腕の見せどころになります。
また、仕分けに関しては、バーコードの読み取りエラーやラベルの貼り間違いが致命傷になります。現場の動きを見て、スキャンエラー時の再印刷・アラート表示など、細かいUX改善を施す必要があります。
出荷締めは“15時〜16時”が勝負
私が担当していた物流センターの多くでは、当日配送の出荷締切は15時〜16時。つまり、それまでにすべての当日配送荷物を梱包・伝票貼付・検品し、集荷バースに並べておかなければならないのです。
この出荷締め時刻から逆算して、「13時にはすべてのピッキング完了」「14時に仕分け終了」「15時前に積み込み完了」など、分単位での作業がタイムチャートとして可視化され、現場とSEの間で共有されています。
実話:たった1時間の“勝負”
筆者が関わった現場の中でも、特に印象に残っているのが、多摩を中心に展開するあるスーパーマーケットの物流センターです。ここでは飲食品の当日配送が日常的に行われており、そのスケジュールの厳しさはまさに“ギリギリの綱渡り”でした。
具体的には、出荷指示が発行されるのが14時。そして最初の配送便が倉庫を出発するのが15時──つまり、ピッキング・仕分け・ラベル貼り・バースへの搬出まで、すべての作業をわずか1時間で完結させなければならなかったのです。
1店舗あたりの配送量も決して少なくありません。テナー(配送用の折りたたみ台車)は1店舗につき20〜30台。2Lペットボトルのケースが山積みされたテナーがズラリと並び、ときには1店舗で20台以上の重たい飲料品が集中することも。現場では「これは機械ではさばけない」とされ、システムよりも熟練作業者の動きがすべてを支えていました。
作業員は時計と睨めっこしながら、「今どの便がどのステータスにあるか」を頭に入れ、台車を自ら仕分け、フォークリフトの走行ルートすら意識して動いていたのです。システムはあくまで補助的。まさに“職人技”の世界でした。
なお、実はその頃の私はSEではなく、現場作業員としてこの“地獄の1時間”に直接携わっていました。熟練作業者のスピードに追いつけず、何度も怒鳴られ、メンタルはボロボロ。それでも「なぜこうなるのか」「どうすればラクになるのか」と考え続けたことが、のちのSEとしての視点につながっています。あれはまさに、苦くも忘れがたい経験でした。
SEが果たす“裏側の自動化”
このタイトな流れを支えるのが、自動化されたシステムの連携です。具体的には以下のような仕組みが実装されています:
- 9時ちょうどの定時バッチで受注確定処理と波形抽出
- ピッキング指示と伝票番号の自動紐付け
- WMS→TMS連携により配送ルート自動判定
- 仕分け棚の可視化、ラベル自動印刷
- 集荷時間10分前にアラート表示+未完了件数の自動通知
現場のオペレーションを“1分も無駄にしない”設計にすることで、初めて当日配送は現実的な選択肢になるのです。
まとめ
当日配送は、単なるスピード競争ではありません。その裏側には、秒単位のオペレーションと、システムによる緻密な連携、そして現場との綿密なコミュニケーションがあります。物流の世界では「遅れる=損失」と直結し、感覚ではなく、ロジックで動いています。
社内SEの立場では、業務の流れを正確に把握し、無理のないタイムテーブルと自動化の導入で現場を支えることが重要です。「スピードは無理に出すものではなく、設計で生まれるもの」──それを体感できるのが、当日配送の現場です。
私たちはつい、「出荷が遅れたのは現場のせい」と考えがちですが、実際にはその原因の多くが“設計ミス”や“想定不足”にあります。当日配送は、現場力だけでなく設計力の集大成。だからこそ、SEは机上で完結せず、現場に足を運び、声を聞き、秒単位の動きを可視化しなければならないのです。
「速くする」ではなく「無駄をなくす」設計こそが、物流の未来を変える鍵となります。

ギリギリだけど成立する。当日配送ってまさに“綱渡りの芸術”ですね😅でも、そこにSEの工夫があると思うんです。
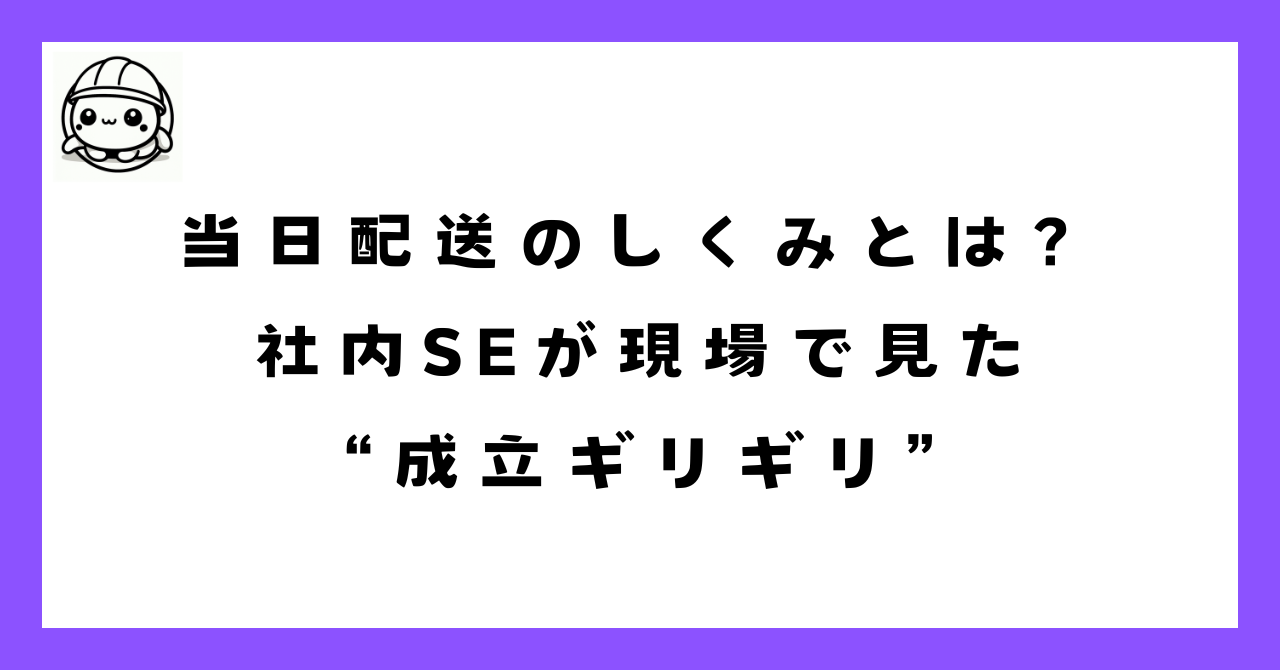
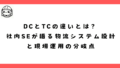
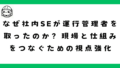
コメント