はじめに
「朝だけ忙しい」「15時から一気に作業が集中する」──現場の作業量には必ず波があります。この“波動”を放置したままだと、ある時間帯だけ疲弊し、別の時間帯は手持ち無沙汰という“アンバランスな現場”が生まれてしまいます。
この記事では、社内SEとして実際に取り組んだ“作業時間の平準化”の事例と、その裏側にあるシステムとシフト設計の工夫について紹介します。「忙しさの偏りをならす」ことで、現場はもっと持続可能になります。

「手が足りない」と「手が余る」が同時に起きると、現場は疲弊しちゃうんですよね😓
作業時間の平準化とは?
平準化(へいじゅんか)とは、作業量のばらつきや波動をならし、一定のリズムで作業を進める状態を指します。生産管理や物流の分野では特に重要視され、「人員配置」「作業指示」「納品タイミング」などを調整して、ピークを分散させる施策として用いられます。
ただし、現場は刻々と変化します。月初・月末、午前・午後、キャンペーンや悪天候など、一定にならないのが現場の常です。その中でも「ならせる要素」と「調整できる手段」を見極めるのが、SEの腕の見せ所です。
事例①:荷下ろし集中を分割して分散
ある倉庫では、午前9時にトラックが3台一斉に到着し、同時に荷下ろしが始まっていました。フォークリフトも人手も足りず、「午前中だけ異常に疲れる」という状態に。
私は配送ルートと納品スケジュールを調整し、1台は8時半、もう1台は10時着に変更。さらに、荷下ろし指示も30分単位で可視化。結果として作業時間が平準化され、午前の残業が0になりました。
事例②:可視化が人員配置を変えた
作業のピーク時間帯はわかっていても、具体的なデータがないと人員調整は難しい──そこで、私はGoogleフォーム+スプレッドシートで「30分単位の作業量」を日々記録。これをヒートマップで表示することで、月間の波動を一目で見える化しました。
この可視化により、特定曜日・時間に作業が集中していることが判明。繁忙時間帯にパートシフトをずらすことで、ミスと滞留が激減しました。
社内SEが支援できること
現場の平準化は、単に「人を増やす」「作業を速くする」ことでは解決できません。作業を均すには、情報と時間の再設計が必要です。
- 作業波動のログ取得とヒートマップ化
- 出荷・納品スケジュールとの連携による前倒し調整
- ハンディ端末や作業端末によるリアルタイム進捗の把握
- Excelで作られていたシフト表の自動化、変動対応のしやすさ向上
こうした仕組みを現場に合わせて導入することで、限られた人員でも効率的に動ける体制が構築されます。
まとめ:「ならす」は“仕組み”でしかできない
作業波動をならすには、“人の頑張り”ではなく“仕組みの設計”が必要です。荷物の波、人の波、タイミングの波──これらをデータでとらえ、判断し、整える力こそが、社内SEに求められる役割だと感じています。
平準化された現場は、無理がなく、持続可能で、誰にとっても働きやすい場所になります。もし今、どこかに“集中して大変な時間”があるなら、そこにはきっと、ならすための工夫が眠っているはずです。

「ならす」って、けっこう静かだけど、現場を守る強い設計なんですよね😊
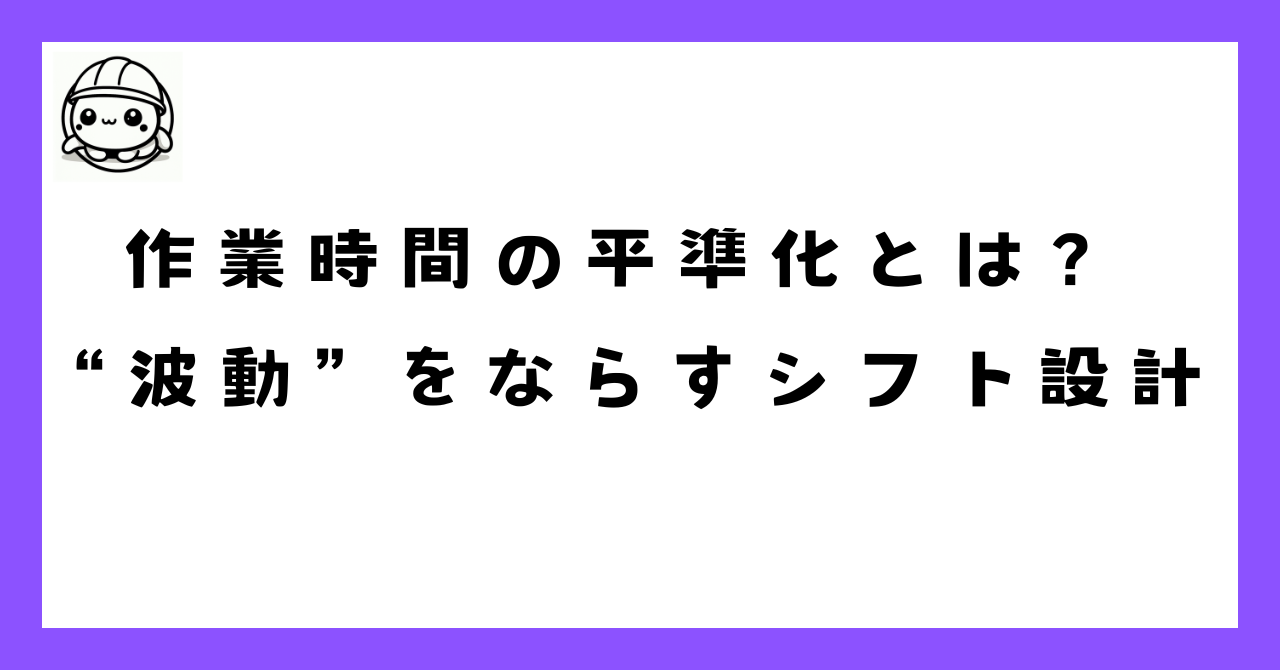
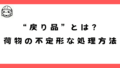
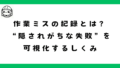
コメント