はじめに
「これ、返品じゃないんだけど…」「一時的に戻ってきただけなんです」──物流や小売の現場では、明確な“返品”ではない、いわゆる“戻り品”というグレーな存在が扱われることがあります。
この“戻り品”の取り扱いは、現場判断にゆだねられていることが多く、システムや帳票にうまく載せられない厄介な存在です。この記事では、社内SEの視点から“戻り品”をどう整理し、現場の混乱を減らしたかを具体的にお話しします。

“返品じゃない”けど“戻ってくる”──これ、扱いがほんとに難しいんです…😅
“戻り品”とは何か?
“戻り品”とは、正式な返品処理ではないが、何らかの理由で一度出荷された商品や資材が倉庫や店舗に戻ってくるケースを指します。代表的なものには以下があります:
- 納品先の都合で一時的に持ち帰った商品(例:受け入れ不可、納品先変更)
- 貸し出し品・什器類の返却
- 陳列後に引き上げた季節商品の在庫戻し
- 未開封での再販可能商品だが返品伝票が存在しないもの
一見「返品」と似ていますが、返品処理フロー(返品伝票、仕入返品処理、在庫マイナスなど)とは異なり、「扱いが曖昧」であることが最大の問題です。
問題点①:棚に入れていいの?判断が分かれる
ある現場では、戻り品が無言のまま仮置きエリアに積まれ、「これは再出荷用?返品品?再販可能?」と混乱を招いていました。誰も判断できず、結果として在庫にも計上されず、実物だけが倉庫に残るという“情報不在”の状態が発生していたのです。
この状態を防ぐため、私は「戻り品ラベル」を導入。戻し理由・状態・再販可否を記載し、棚入れ時にフラグを立てる形式に変更しました。これにより、再販可能なものは即補充、不可なものは隔離棚へ──という明確な動線を作れました。
問題点②:システム上“存在しない在庫”になる
戻り品は、出荷伝票がキャンセルされたわけでも返品伝票が発行されたわけでもなく、システム上は「存在しない在庫」になってしまう場合があります。そのまま棚に戻すと、帳尻が合わなくなり、在庫差異やダブり登録が発生する危険があります。
そこで私は、戻り品専用の一時的な“仮在庫ロケーション”を定義し、戻った時点でそこに移す処理を構築。入荷検品と同じフローで登録することで、在庫管理上の整合性を確保しました。
問題点③:返品と混同され、誤処理される
現場の担当者が「戻ったから返品」として処理し、仕入先への返品扱いで伝票を発行してしまった事例もあります。これは損益にも影響するため、情報伝達の齟齬が大きなリスクとなります。
この対策として、戻り品は返品処理とは明確に別の受付画面・伝票種別に分けることを徹底。ステータス管理(戻り品/返品処理中/保留)をシステムに組み込むことで、誤処理が起こらないようフローを整備しました。
まとめ:“戻り品”をシステムに載せる設計力
“戻り品”は、あいまいで扱いづらい存在ですが、現場では頻繁に発生するリアルな業務です。ルールがなければ属人化し、ミスがあれば在庫差異・売上誤計上・損益ズレといった深刻な問題に発展します。
社内SEとしては、「例外だからこそ拾い上げる仕組み」が必要です。返品ではない、出荷ミスでもない、けれど“戻ってきた”荷物。これをステータス管理し、明確な処理ルートと識別方法を設計することで、現場の安心感と経理・販売管理の正確性を両立できます。
戻り品対応は“例外”であると同時に、“しくみの盲点”でもあります。だからこそ、日常に潜むこの不定形な業務に、丁寧に手を入れていくことが、社内SEとしての真価を発揮する場なのです。

“戻っただけ”の荷物こそ、しっかり記録しないとダメなんです📦

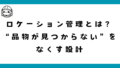
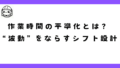
コメント