はじめに
物流現場におけるシステム設計を考えるうえで、避けて通れないのが「DC(ディストリビューションセンター)とTC(トランスファーセンター)の違い」です。この2つの拠点は、物流戦略の根幹に関わるものであり、設計思想も業務フローもまったく異なります。
この記事では、物流システムの内製開発を担当してきた社内SEとして、DCとTCの違いをシステム設計・運用の視点から具体的に解説します。単なる「保管型」と「通過型」の違いにとどまらず、現場で何が起きているのか、その差がどのように業務プロセスに影響を与えるのかを深掘りしていきます。
DCとは何か?
DC(ディストリビューションセンター)は在庫を持ち、保管・ピッキング・梱包・出荷を一括して担う拠点です。多くの小売業や通販物流では、DCを基点に商品を一時保管し、注文に応じて商品を仕分けて出荷する形式をとります。
在庫の保有と管理が中心となるため、在庫精度・ロケーション管理・棚卸業務・賞味期限管理など、システム要件も高くなります。WMS(倉庫管理システム)においても、DCに求められる要件は複雑で、リアルタイムな在庫反映や波動対応の設計が重要になります。
TCとは何か?
TC(トランスファーセンター)は通過型の拠点であり、基本的に在庫を持たず、入荷した商品をそのまま各店舗や取引先に仕分けて出荷します。TCの使命は「通過速度」。つまり、どれだけ迅速に、かつ正確に商品を流せるかがポイントになります。
このため、TC向けのシステムは在庫管理よりも「仕分け指示」「配送先別ラベリング」「タイムスロット管理」などが中心になります。入荷データと出荷先の対応付け処理(スルー仕分けロジック)が命であり、リアルタイム処理やラベル印刷の精度・速度が要求されます。
DCとTC、現場の“本当の違い”
システム的な構造の違いだけでなく、DCとTCではオペレーションのリズム、現場担当者の考え方すら異なります。DCでは「在庫をどう守るか」が中心ですが、TCでは「ミスなく時間通りに流す」が至上命題です。
たとえば、DCの棚卸作業は1日がかりでも許容されることがありますが、TCでの仕分け遅延はそのまま配送遅延につながり、クレームや損害に直結します。この温度差は、SEにとってもシステム設計における最重要視点となります。
設計の分岐点:共通化か、専用化か
実務では、DCとTCを1つのWMSで共通管理するか、それぞれ専用に構築するかという分岐点があります。前者はシステム開発・保守コストが下がりますが、現場との乖離が大きくなりやすい。後者は現場ニーズに密着しますが、リソースが分散します。
筆者は、初期は共通化しながらも、「出荷処理」「入荷ロット処理」「ラベル設計」などの要件はTC専用に分けるハイブリッド方式を採用しています。カスタマイズの負担と、業務現場の実行性のバランスをとる設計が求められます。
まとめ
DCとTCは、物流拠点の機能としては似て非なる存在です。在庫を持ち管理するDCと、通過させることに特化したTCでは、要求されるシステムも、現場のKPIも、責任の所在も大きく異なります。
SEが物流現場のシステムを設計する際には、単なる拠点分類としてではなく、そこで働く人々の動きや、発生するトラブル、求められるスピード感に対する理解が不可欠です。特にWMSやEDI、配送連携においては、この理解が機能設計や業務フロー設計に大きな影響を与えます。
単に「DCかTCか」で切り分けるのではなく、それぞれの特徴を活かしつつ、いかに現場にとってストレスの少ない運用をつくるか。答えは現場の声にあります。開発の都合ではなく、業務の都合を優先すること──これこそが、社内SEが“物流のリアル”と向き合ううえでの基本姿勢なのです。

設計するとき、「ただ通せばいい」じゃ済まないんですよね。TCってスピード命だから、仕分けロジックとラベル周りは本当に重要!😊
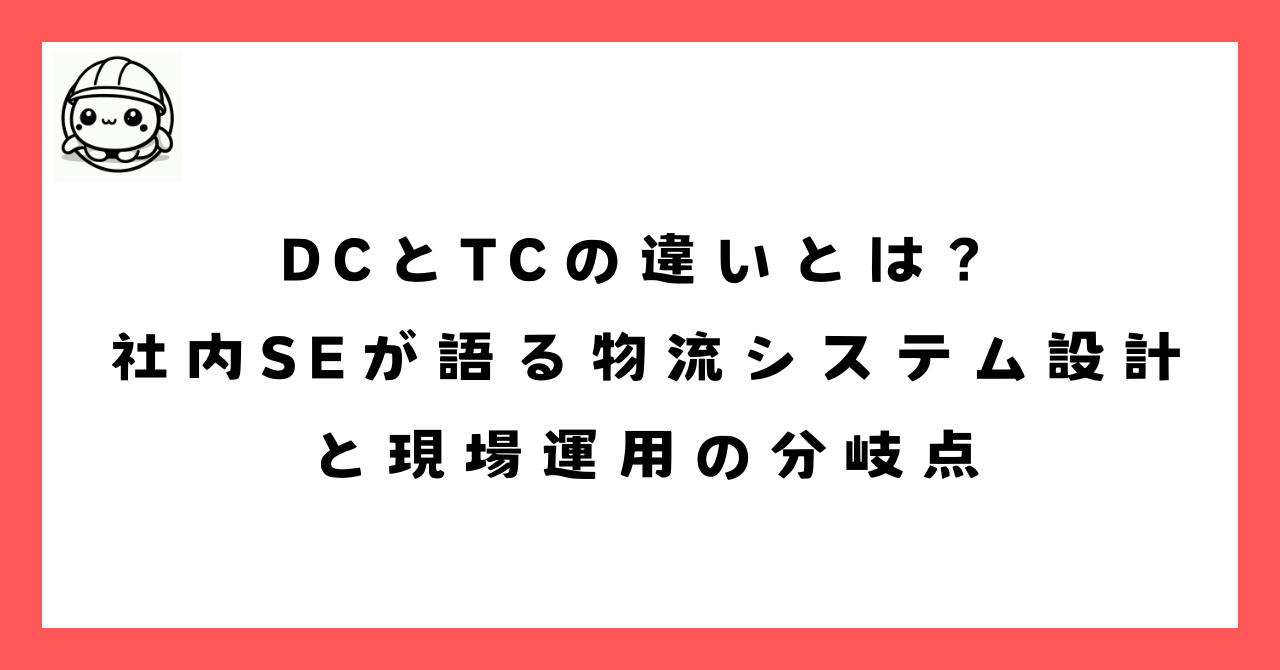
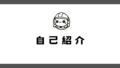
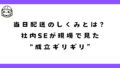
コメント