はじめに
「このケース、システムでは拾えませんね…」──そんなセリフが現場で交わされるとき、それは“例外対応”の始まりです。私は社内SEとして現場とシステムのはざまに立ち、何度も「仕組みでは救えない困りごと」と向き合ってきました。
この記事では、現場で発生する“例外”の正体と、それにどう向き合えばいいのか。しくみ化と柔軟性のバランスをどう取るのか。実際の事例を交えながら、社内SEの視点でお話しします。

“例外対応”って、結局どこまで拾うのが正解なのか…悩ましいテーマなんです😊
「例外」とは何か?
業務の中で言う“例外”とは、標準的なフローやシステムの想定外に発生するケースのこと。たとえば:
- 予定外の返品が到着した
- 出荷先が急に変更された
- 不在票の対応で特別フローが必要になった
こうした事態は、頻度が少ないためにルール化されておらず、“人の判断”に委ねられます。そして、その判断は属人的になりがちです。
事例①:伝票にない「口頭依頼」をどうする?
ある現場では、特定の得意先から「この品は別便で送って」と口頭で依頼されることが頻発していました。しかしシステムにはその指示が反映されないため、現場では付箋やメモで個別に対応。
私はその状況を見て、オペレータが“伝票にない一言”を記録できる自由記入欄をシステムに追加しました。すると、現場での確認や共有が格段にスムーズになったのです。
事例②:「在庫なし」とされたけど、実は奥にあった
在庫検索で「在庫なし」と表示された商品が、実際には棚の奥や別保管場所にある──というケースも多発していました。
そこで「現場で見つけた在庫」を登録する機能と、コメント付きで再登録できる仕組みを導入。棚番や発見者の情報も一緒に記録され、在庫精度が飛躍的に改善しました。
事例③:システムに入れたくない“人の配慮”
たとえば「この人にはやさしく声かけしてね」といった、マニュアルにもデータにも載せづらい情報──これも立派な“例外対応”です。
私は、現場のスタッフが気軽に情報を残せる「ヒト情報メモ」機能を提案。名前と連動した簡易メモが、次回対応時にポップアップ表示される仕組みにしました。小さな工夫ですが、現場の配慮と安心感をつなぐ効果がありました。
まとめ:例外は「悪」ではなく“気づきのきっかけ”
例外対応は、仕組みからこぼれた“問題”ではなく、現場が工夫して補っている“知恵”です。むしろ例外が頻発する領域こそ、システム改善のヒントが詰まっている場所。
だからこそ社内SEとしては、例外を「排除する」のではなく、「拾い上げて意味づける」姿勢が求められます。記録の形式を変える、メモ欄を用意する、ポップアップで補助する──小さな仕掛けで、“しくみの外”にいる人をつなぐことができるのです。
最終的なゴールは、“例外を例外でなくすること”。それが、現場の声を受け止め、改善を重ねる社内SEの役割だと私は感じています。

しくみにできないことにこそ、ヒントがあるんですよね😊
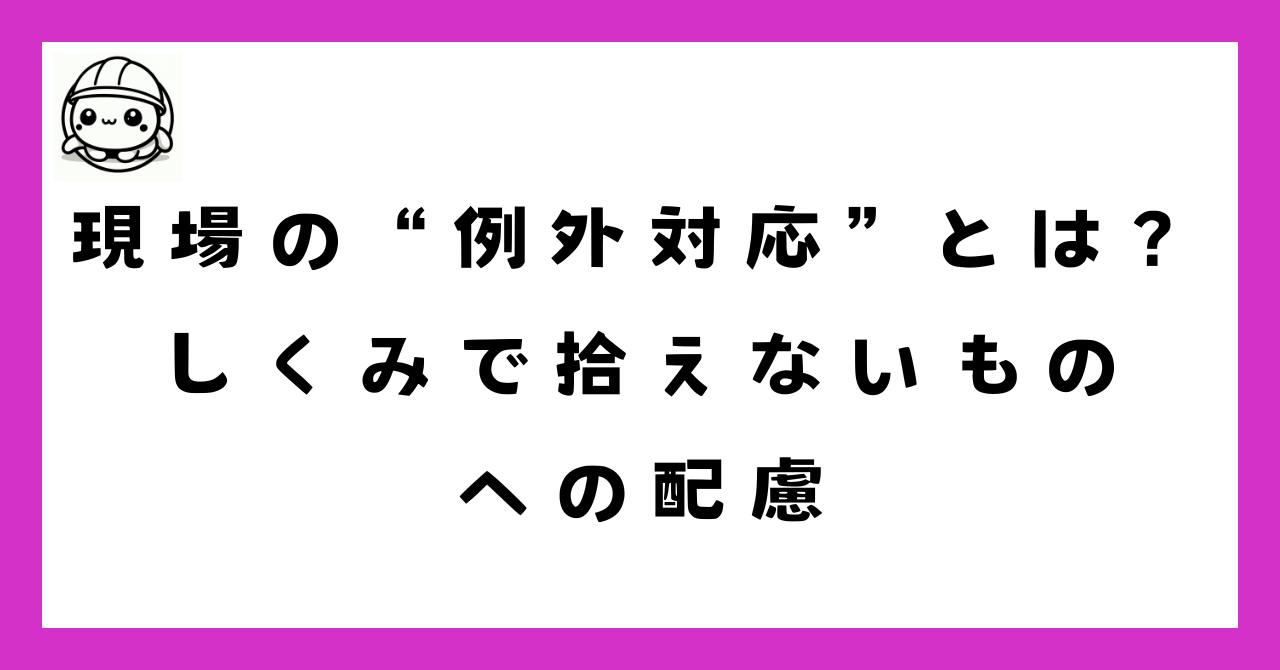
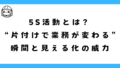
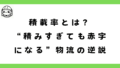
コメント