はじめに
ITエンジニアが取得する資格といえば、基本情報技術者や応用情報、ネットワーク系の資格を思い浮かべる方が多いかもしれません。しかし、私はかつて運行管理者という少し異色な資格を取得しました。
なぜ社内SEが運行管理者の資格を取ったのか?本記事ではその理由と背景、そしてどのように業務に活かせたのかを、実体験をもとにご紹介します。
運送会社での社内SE経験
配属先は物流現場
私は以前、ある運送会社で社内SEとして業務改善を担当していました。しかし、その企業では「まずは現場を知れ」という方針があり、入社当初はドライバーの業務や配車管理の補助など、物流の現場に配属されました。
運行管理者の資格取得を勧められる
現場業務に携わる中で、配車や労務管理に関わるルール・制度の複雑さを痛感しました。とくに業務改善やシステム導入に関わるには、運行管理者としての基礎知識が不可欠。そうして、上司からの勧めもあり、資格取得を決意しました。
TMS導入に必要だった視点
TMSとは?
TMS(Transportation Management System)とは、配車計画、配送管理、運転手の労務管理などを統合的に管理できるシステムのことです。導入によって、作業の効率化・見える化・法令遵守が図れます。
技術だけでは選定できない
TMSの導入にはシステム的な知識だけでなく、実務の流れや法令、ドライバーの運行ルールに対する理解が不可欠です。運行管理者として学んだ内容が、実際の業務に深く結びついており、机上の空論で終わらない提案ができるようになりました。
ニーズに応えるTMSの選定・導入
現場と連携したヒアリング
資格取得後は、現場の担当者と同じ目線でTMSの要件定義を行うことができました。運転手の拘束時間管理や点呼記録、乗務記録といった運行管理業務も含めたシステム選定が可能になり、結果として現場にマッチしたシステム導入が実現しました。
導入後の効果
導入後は、配車業務の効率化、法令遵守の確実性向上、手作業による記録の削減など、多くの効果が現れました。運行管理者の視点があったからこそ、使えるTMSを選べたのだと実感しています。
まとめ
社内SEが運行管理者の資格を取る、一見すると、IT職と直接関係のない、ミスマッチな選択に見えるかもしれません。ですがこの資格取得は、現場を深く理解し、業務改善をより現実的に進めるための、大きな武器となりました。
社内SEという立場で業務改善やシステム導入を提案する際、「現場を知らない人の意見」と見られてしまうことは少なくありません。とくに運送業のような現場主導・属人性の高い業務フローでは、机上のIT提案が受け入れられにくいという壁に何度もぶつかりました。
そこで「業務そのものをもっと理解したい」と考え、実際に運行管理者の資格を取得し、運送計画や労務管理、安全対策といった業務知識を体系的に学びました。その結果、現場の課題や感覚がより具体的に見えるようになり、「現実に即した改善案」が出せるようになりました。
資格取得自体がゴールではありませんが、「ITを使う側の視点」を持ったうえで仕組みを考えることの重要性を、あらためて実感した経験でもあります。
ITだけでは業務は変わらない。現場を知り、現場に寄り添うことが、社内SEとしての価値を高める近道なのかもしれません。

運行管理者の資格、けっこう勉強大変でしたが💦、取ってみたらめっちゃ現場と話しやすくなりました!SEこそ現場に入るの、大事だと思います😊
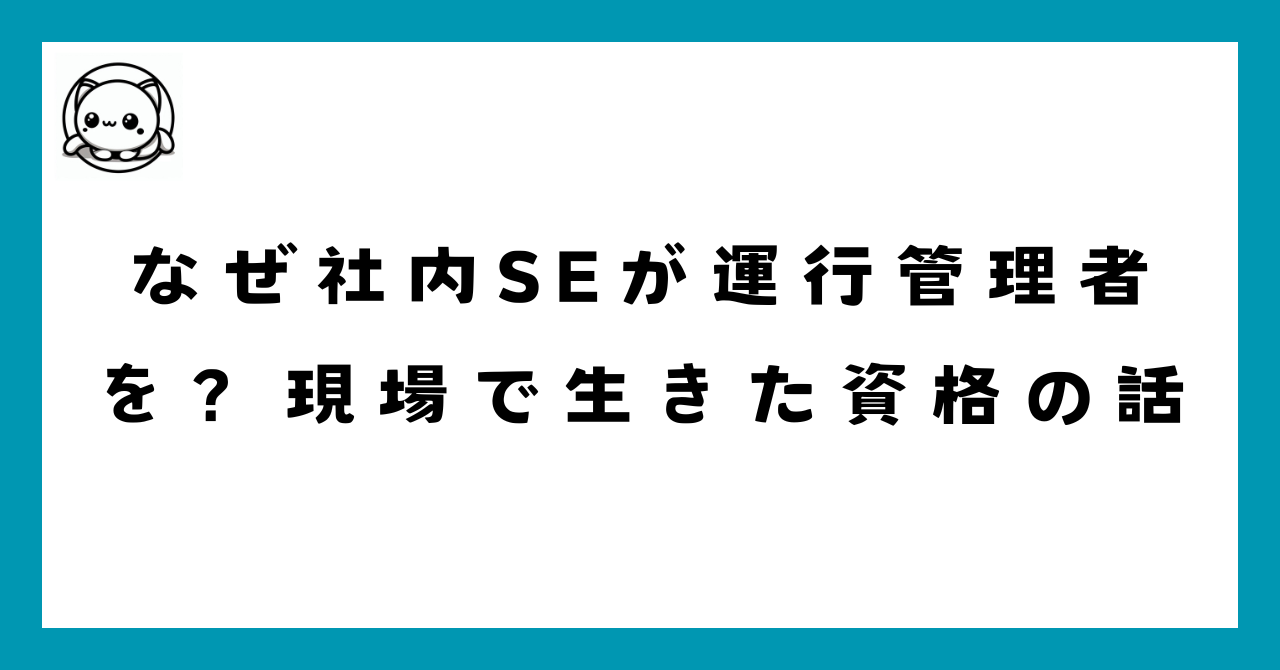
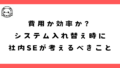
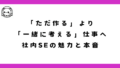
コメント