はじめに
年に1回~数回行われる法定点検やビルの電気設備更新工事などによる計画停電。これらは事前に告知されるものの、社内SEや情シス担当者にとっては要注意のイベントです。停電前後に何をすべきかを整理しておかないと、再起動後に「PCが起動しない」「モニターが映らない」といったトラブルに見舞われることもあります。
停電前に社内SEがすべきこと
1. 対象フロア・機器の確認
まずは、停電の影響を受ける範囲(フロア、サーバールーム、LAN機器周辺など)を明確にしましょう。自社ビルでなく賃貸オフィスの場合は、ビル管理会社からの通知をもとに対象エリアを特定します。
2. 対象機器のリストアップ
UPSがついている機器や、電源が常時ONのもの(サーバー、複合機、NAS、ルーター、スイッチングハブ、無停電電源装置など)を一覧化し、どの機器をいつ・誰が電源OFFするかを明確にしておきましょう。
3. モニターやPCの電源もOFFにする
意外と忘れがちなのが、モニターやデスクトップPC、ディスプレイアダプタなどの電源OFFです。停電直後の瞬間的な電圧変動により、モニターのバックライトが破損するなどの報告例があります。使用頻度の低い周辺機器も含めて、できる限り電源を落としておきましょう。

「停電ってどうせすぐ終わるでしょ」なんて油断は禁物です!復電時にモニターが真っ暗…なんて話もあるので、慎重に電源OFFしてます。
復電後にすべきこと
1. 安全確認後に機器の通電を
通電直後は一時的に電圧が不安定になることがあります。まずはブレーカーや分電盤の復旧状況を確認したうえで、ネットワーク機器やサーバーの順番を考慮しながら、1台ずつ慎重に電源を入れていきます。
2. トラブル発生時の初動体制
モニターが映らない、ファンが回らない、NASがマウントされないといったトラブルが発生する場合があります。復電日の午前中は、可能であれば出社して確認できる体制を整えておきましょう。

復電後って、なぜかNASが見えないとか、Wi-Fiだけ繋がらないとか、謎トラブルが起きがちなんですよね…。予備日として午前中は空けておくのが安心です。
まとめ
停電はただの電気工事ではありません。社内SEにとっては、日頃当たり前のように使っているITインフラが一時的にシャットダウンされる、ある意味で「想定された障害対応」のようなものです。普段から停電時の手順をマニュアル化し、どの機器を誰が対応するか、何時までに行うかを明確にしておくことで、トラブルを最小限に抑えることができます。
特に復電直後は、普段見られないようなトラブルが発生しやすいタイミングです。「いつも通り」が通じない環境下で、焦らず冷静に対応できる準備をしておくことが、社内SEとしての信頼につながります。
あらかじめ機器のリストアップと電源管理、初動対応の確認、そして翌営業日のサポート体制まで。どれも地味ですが、やっておいて損はない対応です。むしろ、「なにごともなく終わった」が理想の結果です。
本記事が、皆さんの現場対応やマニュアル整備の一助になれば幸いです。
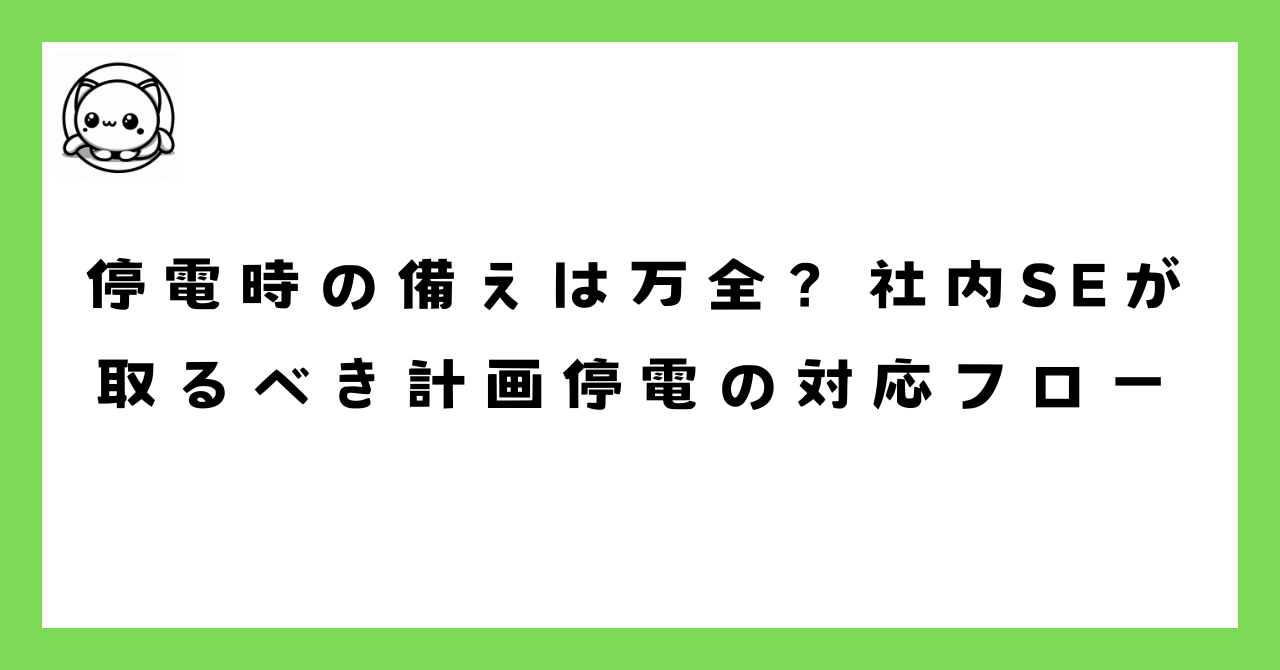
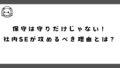
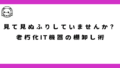
コメント