はじめに
システム導入は業務改善の大きなチャンスである一方で、失敗すると大きなコストと現場の混乱を引き起こします。特に中小企業や社内SEが関わる現場では、「せっかく導入したのに使われない」「むしろ手間が増えた」といった事態も少なくありません。
本記事では、よくあるシステム導入の失敗事例を踏まえつつ、成功するためのポイントを「準備・体制・設計」の観点から解説します。
ありがちなシステム導入の失敗例
1. 現場のニーズと乖離した導入
経営層や上層部が導入を主導し、現場の業務フローや課題を把握しないまま選定・導入が進むと、「使いにくい」「結局、前の方法の方が早い」と現場での定着率が下がります。
2. 導入ありきで進めてしまう
「このツールが流行っているから」「補助金が出るから」といった理由で、具体的な目的やゴールが曖昧なまま導入を進めると、形だけのDXで終わってしまいます。
3. 教育・マニュアル不足
システムを導入しても、使い方の周知やマニュアル整備が不足していると、定着しないどころか「使いたくないシステム」として敬遠されてしまいます。
成功のために必要な準備と体制
1. 現場ヒアリングの徹底
実際の業務を理解するために、現場への丁寧なヒアリングを行い、「困っていること」「繰り返し発生している手間」などを把握することが出発点となります。
2. 小さく始めて、段階的に展開
いきなり全社導入を狙うのではなく、一部部署で試験導入し、フィードバックを得ながら改善していくアプローチが有効です。スモールスタートは失敗リスクを抑え、成功率を高めます。
3. 推進チームの組成
SEだけでなく、現場メンバーやリーダーも巻き込んだ推進体制を整えることで、現場への浸透度が高まります。「一緒に作る」意識を持たせることがカギです。
ユーザー視点の設計がカギ
1. 操作性と導線設計の工夫
いくら高機能でも、ユーザーが直感的に操作できなければ使われません。業務の流れに自然に沿ったUI設計、画面遷移の単純化などが求められます。
2. 現場の“ことば”で設計する
システムに登場するメニュー名やラベル、説明文も、専門用語ではなく現場のスタッフが日常使っている言葉で表現することが大切です。心理的ハードルを下げ、親しみやすい印象を与えます。
まとめ
システム導入は「何を導入するか」だけでなく、「どう導入し、誰と一緒に育てていくか」が成功のカギです。現場と対話しながら、小さな改善の積み重ねによって、本当に使われる仕組みを目指しましょう。

システムって「入れたら終わり」じゃないんですよね…。最初は面倒でも、使う人と一緒に作っていくと、だんだん現場になじんでいきますよ!私も何度も失敗して学びました😅
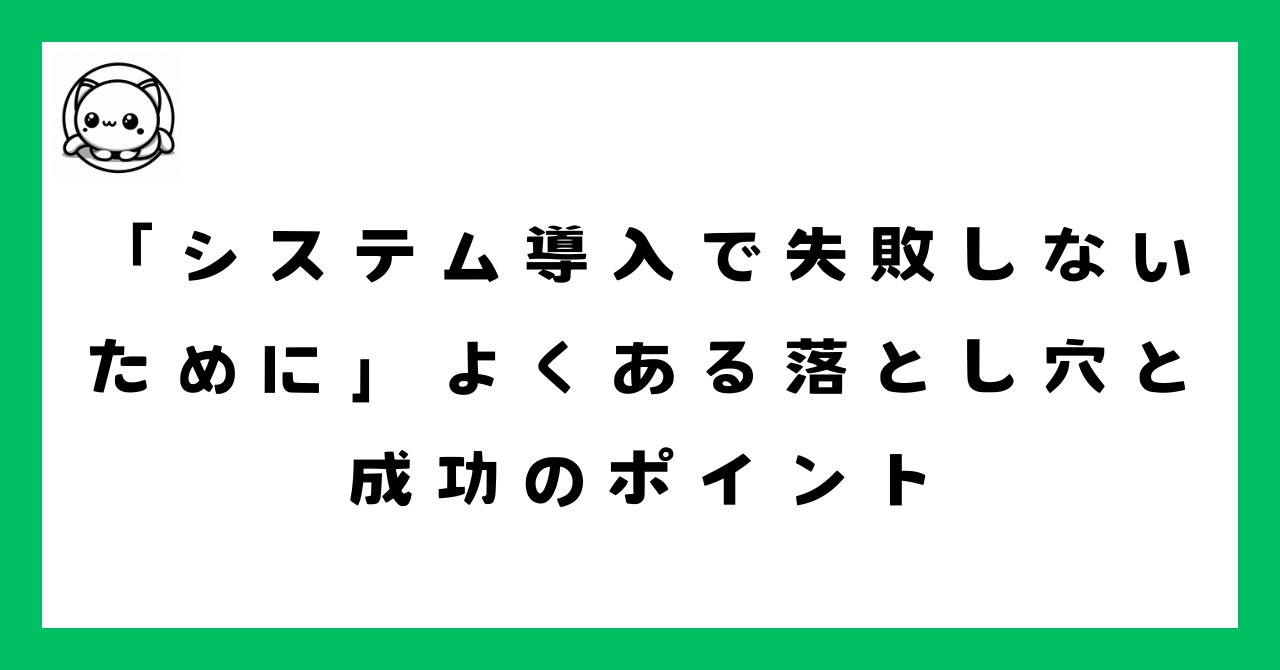
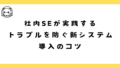
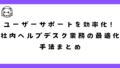
コメント