はじめに
DX化が進む中で、社内SEの役割や存在価値について再び注目が集まっています。しかし、慢性的な人手不足のなか、「本当に社内SEは必要なのか?」という問いを持つ経営者や現場の声も少なくありません。
本記事では、社内SEが果たすべき本質的な役割と、外注との住み分けについて筆者の実体験を交えて考察します。
社内SEは本当に必要なのか?
人手不足の時代、SEを確保すべきか?
技術者不足が続く中、社内SEの新規採用や育成は簡単ではありません。そのため、社内にIT人材を抱えること自体がコストと見なされるケースもあります。
しかし、ITトラブルや導入検討時に即座に対応できる「社内にいるエンジニア」の存在は、業務の安定やスピードに大きく貢献します。

「急ぎの対応お願いします!」って言われると、近くにいるだけで頼られがち。でも、すぐ話せるっていうのも立派な強みなんですよね😅
アウトソーシングとの役割分担
専門技術は外部、調整と要件整理は内部
中小企業においては、サーバー構築やプログラミングなどの専門業務は、外部のプロに任せる方がコストパフォーマンスに優れています。社内SEの役割は、現場の業務要望を汲み取り、ベンダーとの橋渡しを行うIT折衝にシフトすべきです。
ノーコード/ローコードツールの活用
Google Apps ScriptやPower Automateのようなノーコードツールの台頭により、社内SEでもスピーディーな業務改善が可能になっています。重たいシステム開発は外注しつつ、軽微な業務改善は自社で対応できるようにするのが理想です。

ノーコードは最初「なんか軽いな…」って思ってたけど、使ってみるとめちゃ便利。職場のちょっとした「困った」を自分で直せるのは、なかなか気持ちいいんですよ〜
社内SEの本質的な役割とは
現場の声を聞く力が、最大の武器
どれだけ高機能なシステムでも、現場にフィットしなければ意味がありません。社内SEが最も力を入れるべきは、現場の業務フローや課題のヒアリングです。これこそが、外部の技術者にはできない価値提供だと考えています。
要件整理と共感のスキル
ユーザーとの信頼関係を築き、「この人に相談すればわかってくれる」と思われることが、プロジェクト成功の鍵となります。技術力だけでなく、共感力・説明力も社内SEには求められます。
まとめ
社内SEは「なんでも屋」ではありません。社内にいながら現場の声を拾い、必要に応じてベンダーを調整し、小さな改善を積み上げていく“橋渡し役”としての存在が求められています。外注と社内SE、それぞれの強みを活かし、これからのIT環境を支える体制づくりを進めていきましょう。

「開発はプロに、調整は社内で」って割り切ると、すごく動きやすくなりました!社内SEは“つなぐ役”って思うと、やるべきことがハッキリしますよ😊
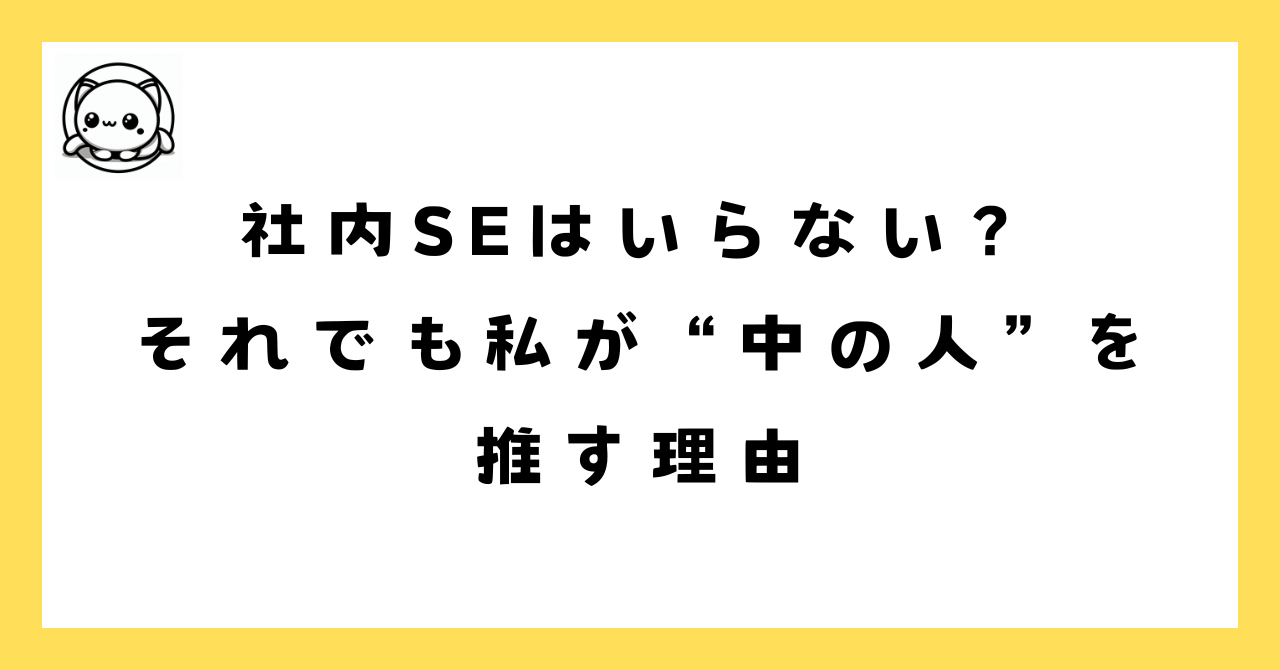
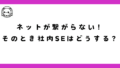
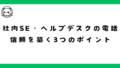
コメント