はじめに
「社内SEの仕事って、どこの会社でも同じでしょ?」とよく言われます。しかし、実際に複数の業種・企業で社内SEを経験してきた立場から言うと、「業務は似ているけど、会社ごとの“違い”は意外と大きい」と感じます。本記事では、物流・販売系など複数の企業で社内SEとして働いてきた筆者が、共通する部分と違いについてリアルな視点で解説します。
業務内容は基本的に共通している
PCやネットワークの保守・運用
社内SEの基本業務として、クライアントPCのセットアップ、メールやネットワークのトラブル対応、プリンタ設定など、いわゆる「情シス」業務はどの会社でも共通です。インフラ整備やセキュリティ対策も担当範囲に含まれます。
社内サーバー・クラウドの管理
Active Directoryの管理や、ファイルサーバーのバックアップ、SaaSのアカウント管理なども標準的な業務です。物理サーバーかクラウドかの違いはあれど、基本的な構成管理・トラブル対応はどこでも必要とされます。
業務システムの維持・改善
基幹システムや業務アプリケーション(販売管理、在庫管理、勤怠管理など)の運用も共通業務です。業種によってシステムの種類や使い方に違いはあるものの、「業務部門の困りごとをシステムで解決する」という本質は共通しています。

やることは似てるけど、「どこまでやるか」は会社によって本当にバラバラ!大企業は分業、小規模企業は一人で全部やる…なんてことも多いです💻
会社ごとの“文化”の違い
何を大切にしている会社か?
たとえば、販売会社では「お客様第一」が徹底されており、業務のIT化よりも対人対応の迅速さが重視されます。一方、物流会社では「効率化」「時間短縮」「データ連携」が重視され、改善活動が日常的に求められます。
社内SEの立ち位置も変わる
社内SEが「頼れるパートナー」としてリスペクトされる企業もあれば、「コストセンター」として低く見られる企業もあります。経営者や上層部がITに理解があるかどうかで、予算や発言権も大きく左右されます。
経営者の考え方が会社の風土を決める
現場重視の社長の会社では、社内SEも現場との距離が近く、業務改善の起点になりやすい一方で、トップダウン型の企業では「IT=コスト」と見られて予算が付きにくいケースもあります。

経営者の「ITってよくわからないし高いよね」って一言で、予算がゼロになったことも…😢 一方で「やりたいことある?自由にやっていいよ」って言われた会社もありました!
まとめ:共通点と“空気”の違いを知ることが大事
社内SEの仕事は、ハード的にもソフト的にも基本的な要素は共通しています。PCのセットアップ、ネットワークトラブル対応、システム保守、データのバックアップなど、やることの“中身”はどこでも似ています。
しかしながら、会社が何を重視しているか、経営層がどんな価値観を持っているかによって、社内SEに求められるスタンスや裁量、働き方はまったく異なります。同じスキルでも、「自分の力を活かしやすい会社」と「ただ言われたことだけをやる会社」がある、ということです。
社内SEという職種は、単なる「裏方」ではなく、会社の文化や方針を写す“鏡”でもあります。複数社を経験したからこそ言えるのは、「自分がどんな社風・価値観の会社で働くのが合っているか」を見極めるのが、長く楽しく働くためのコツだということです。
今の会社でうまくいっていない…と思う方も、それはあなたのスキルが不足しているのではなく、環境とマッチしていないだけかもしれません。「社内SEとして、どんな立場で働きたいか?」を一度立ち止まって考える機会にしてもらえればと思います。
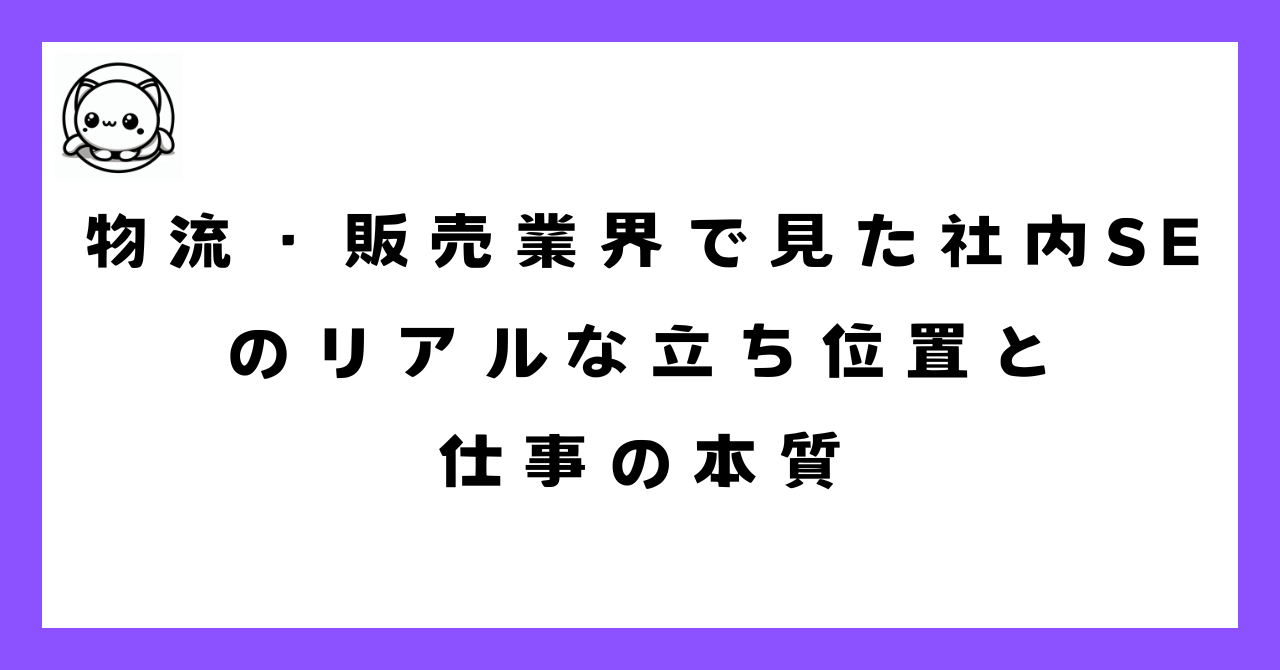
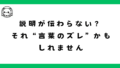
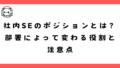
コメント