はじめに
社内SEの役割や立ち位置は企業によって大きく異なります。独立したIT部門として機能している会社もあれば、総務や経理の一部門として存在するケースも少なくありません。本記事では「社内SEのポジション」について、企業ごとの違いや、注意すべきポイントを解説します。
社内SEの配属部署は企業によって異なる
1. IT専門部署としての社内SE
多くの中堅以上の企業では、情報システム部やIT戦略室など、独立した部署に社内SEが配置されています。この場合、組織横断的な視点から全社の業務効率化やインフラ管理、セキュリティ対策に取り組むことが可能です。
2. 管理部門(総務・経理)に組み込まれた社内SE
一方、従業員数の少ない企業では、社内SEが総務部や経理部といった管理部門の一角として配置されることがあります。この場合、IT業務が他の雑務と並列に扱われ、専門性や重要度が軽視されやすい環境になることも。
3. 配属先=経営の方針を映す鏡
社内SEがどこに配置されるかは、会社がITやシステムをどう捉えているかの表れでもあります。「業務の効率化を進める存在」として位置づけているか、「事務の延長」として扱っているかによって、求められる働き方や影響力も変わります。
偏った立ち位置に注意
1. 経理都合のシステム改修
経理部に所属していると、売上計上や帳簿整理のために、他部門の業務効率よりも経理都合が優先されるような開発・改修が発生しやすくなります。システムが特定部門に最適化されすぎると、全社的な使い勝手や公平性を損なう可能性があります。
2. 総務主導によるIT施策の形骸化
総務部に属していると、マニュアル整備や申請フロー作成など、ルール重視の業務が優先される傾向にあります。ITの柔軟性や現場の声を反映しにくくなり、現場からの不満や形骸化した制度を生み出す原因になることも。
理想のポジショニングとは
社内SEは、あくまで全社最適を目指す存在であるべきです。特定の部門に偏るのではなく、経営層・現場・管理部門の“橋渡し”として機能するためには、一定の独立性と裁量が必要です。少人数の企業であっても、社内SEに明確な役割と方針が示されることが、健全なIT運用につながります。

「システム部って名乗ってても、実態は“何でも屋”なんです…」っていう話、よくありますよね。だからこそ、自分のポジションは自分で守る意識も必要なんです💡
まとめ
社内SEの配属部署は、企業の規模や体制によって異なりますが、それが社内SEの使命や影響力を大きく左右することは見逃せません。経理部・総務部に属している場合、部門にとって都合の良い働き方が優先されがちであり、結果としてシステムの公平性や運用の柔軟性が損なわれるリスクがあります。
理想的な社内SEのポジションとは、業務部門・管理部門・経営層とバランスよく連携しつつ、全社最適の視点を持って行動できること。そのためには、組織からの期待値を明確にし、自らの立ち位置を言語化し、場合によっては「そのやり方は業務全体にとって最適か?」と問いかけられるような“芯”を持つことが求められます。
部署の名前に惑わされず、与えられた立場でどう動くか──それが、信頼される社内SEへの第一歩なのです。

最初は「雑用係」から始めた私も、気づけば業務改善の相談が来るようになってきました。ポジションは会社任せだけど、信頼は自分で築いていけるものなんですね😊
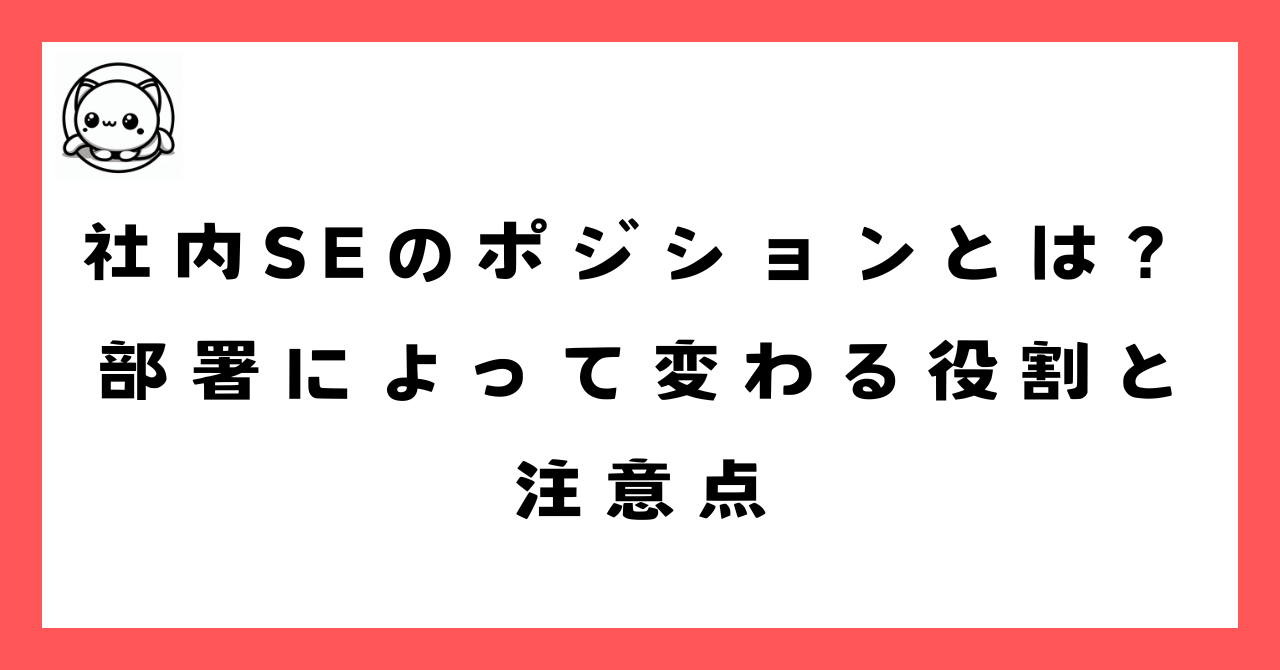
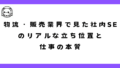
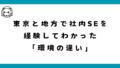
コメント