はじめに
「システムは動いているから大丈夫」「今は問題ないから触らない」──そんな考えが社内に根づいているとしたら、危険信号です。社内SEにとって保守運用は重要な業務のひとつですが、それだけに留まっていると、将来的なリスクやコスト増大を招く可能性があります。
本記事では、社内SEが「守り」の姿勢だけでなく、「攻め」の視点も取り入れるべき理由や、定期的なリファクタリング・改善の必要性について解説します。
保守=静的対応ではない
保守運用の役割とは?
社内SEにとって、障害の予防・検知・復旧は基本です。ログの監視やバックアップ、アップデート管理など、安定稼働を維持する「静的な対応」は確かに重要です。
でも、それだけでは不十分
「今は問題が起きていないから」という理由で何も手を加えないと、ブラックボックス化が進み、トラブル時の対応が難しくなります。技術的負債の蓄積も避けられません。
リファクタリングのすすめ
リファクタリングとは?
機能を変えずにコードを整理・最適化すること。特に内製システムを運用している場合、初期実装時の暫定対応やスパゲッティコードを見直す良い機会です。
定期的に行うべき理由
- 属人化を防ぐ(→誰が見ても理解できるコードへ)
- 後から機能追加しやすくなる
- セキュリティホールの予防になる
改善の視点を持つこと
保守の延長にある改善活動
保守運用は「現状を維持する作業」ではなく、「将来のトラブルを防ぐ施策」でもあります。ちょっとしたスクリプトの自動化や、手作業の排除、定期的な見直しもすべて改善活動の一部です。
改善の時間は意識しないと取れない
目の前の障害対応や依頼対応に追われると、改善のための時間が後回しになりがちです。意識的に「改善のための時間」をスケジュールに組み込むようにしましょう。
まとめ
社内SEとしての「保守」は、単なる維持作業にとどまってはいけません。静的な対応を繰り返すだけでは、トラブルの根本原因を見逃したまま、技術的負債を蓄積してしまうリスクがあります。
とくに内製システムを抱えている現場では、「問題が起きてから直す」ではなく、「問題が起きる前に整える」視点が求められます。そのためにも、リファクタリングや業務改善は定期的に取り組むべき重要な保守活動の一環です。
属人化を避け、保守が楽になり、将来の更新や連携もスムーズに行えるようになります。保守とは「現状維持」ではなく「未来を守る攻めの姿勢」。これを意識するだけで、社内SEとしての仕事の質も評価も大きく変わってくるはずです。

「動いてるからそのままでいいでしょ?」って言われがちだけど、未来を守るには手入れが必要。私も最近ようやくリファクタリングの大切さがわかってきました…🛠️
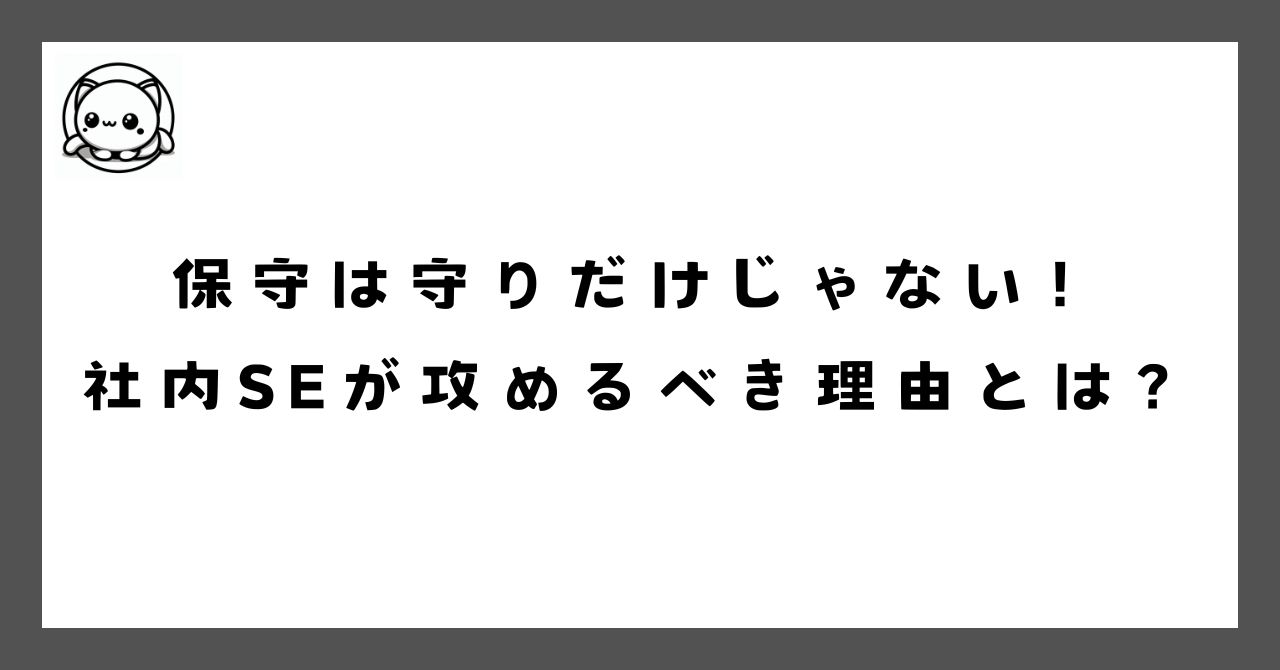
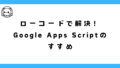
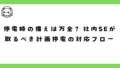
コメント