はじめに
「社内SEは会社に常駐するもの」というイメージを持っている方も多いかもしれません。しかし、すべての会社において常駐が絶対に必要かというと、必ずしもそうではありません。この記事では、実際に複数の会社を担当している現役社内SEの視点から、常駐の必要性について解説します。
現役社内SEの立場から
グループ5社を1人で担当
私は現在、地方の商社で社内SEとして勤務しており、同グループの5社にまたがる情報システム業務を1人で担当しています。それぞれ業種や業務内容が異なるため、問い合わせの内容も多岐にわたります。
常駐は「必須」ではないケースも
社内SEの主な役割には、PCやネットワークのトラブル対応、アカウントの管理、業務システムの運用保守などがあります。これらはリモート対応が可能なものも多く、常に現地にいる必要はない場合もあります。
常駐しなくても成り立つ体制とは
1. マニュアル整備と自助力の強化
よくある質問や操作手順についてマニュアルを整備しておくことで、現場での自己解決を促すことができます。Googleドライブや社内Wikiを活用し、検索しやすくしておくのがポイントです。
2. 不具合を未然に防ぐ設計と導入
使用機器の選定は非常に重要です。安価でも故障の多い機器を避け、サポートの手厚いメーカーや実績のある製品を選ぶことで、日常的なトラブルの発生を抑えることができます。
3. 一部業務の外注化
システム開発やサーバー保守など、リソース的に負担が大きい部分は信頼できる外部ベンダーに委託することで、常駐せずとも安定した運用が可能になります。
ヘルプデスクの役割と対応体制
社内SEは現場からの問い合わせ対応、いわゆるヘルプデスクとしての役割も担います。電話やチャット、リモート操作ツールを活用して、迅速な一次対応ができる体制を整えておくことが重要です。

「社内SE=常駐してなんぼ」って思われがちですが、実はやり方次第で非常駐でもバッチリまわります!私は一度もグループ全社に常駐したことがないですよ〜🧑💻
まとめ:社内SEにとって「常駐=正解」ではない
社内SEがすべての会社に常駐する必要はありません。大切なのは、常駐しなくても業務が滞らない体制を作れるかどうかです。マニュアル化や不具合予防、ツールの整備、そして必要に応じた外注などを組み合わせることで、1人でも複数社を効率よくサポートすることは可能です。
もちろん、業種や組織規模によって最適な対応は異なりますが、社内SEの働き方はもっと柔軟であって良いはずです。「うちのSEはいつもいるのが当たり前」と思われている会社ほど、今こそ体制の見直しが必要かもしれません。
非常駐でも支障のない現場づくりは、社内SEの負担軽減だけでなく、全社的な業務効率や安定性にもつながります。ぜひ、自社の体制を見直すきっかけにしてみてください。

業務量を見極めて、効率よく!「1人で5社やってる」と言うと驚かれますが、要は“仕組み”次第なんです。やればできる、やらなきゃ回らない、それがたまのSEの現場です😅

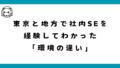
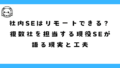
コメント