はじめに
コロナ禍を経て「社内SEもリモートワークできるのでは?」という声が増えてきました。ですが、実際にはどうなのでしょうか?この記事では、現在筆者が勤務している地方の商社において、グループ会社5社の社内SE業務を1人で担当している実情から、リアルな視点で「社内SEのリモートワークの可否」についてお話しします。
社内SEの仕事内容と物理的な限界
機器のキッティングや初期設定
新入社員のPC準備や、プリンタの入替、VPN機器の設置など、現地でしかできない業務は確実に存在します。キッティングや環境構築には、細かな確認や相手とのすり合わせが必要で、現場対応が避けられません。
打ち合わせ・ヒアリングの難しさ
現場の従業員とのちょっとした会話や、役員・管理職への口頭相談など、日々の「すり合わせ」が重要なケースも多く、これがオンラインだけでは難しい場面もあります。
突発的なトラブル対応
「急に印刷できない!」「ネットが切れた!」など、突発的な対応は、現場にいないと対応しづらいことも。特に役員や管理職からの急な呼び出しなど、即応性が求められる場面は一定数あります。
リモート対応の可能性はあるか?
電話・チャット・リモートデスクトップで大半は対応可能
一方で、社内からの問い合わせ対応や設定変更の多くは、電話やチャット、リモート接続で対応が可能です。リモートデスクトップやVPN経由での作業が整っていれば、常駐しなくても対応可能なタスクは確実に増えています。
現場に行かなくても済む仕組みづくりがカギ
物理的な対応が必要な場面を除き、「行かなくてもよい状態を作る」ことは十分に可能です。たとえば、マニュアル化や、操作ミスを減らすUI改善、壊れにくい機器の導入、さらには一部外注化などによって、社内SEのリモート比率を高めることができます。

「リモートじゃムリ」と思われがちな社内SEの仕事も、工夫しだいでかなりの部分が対応できます!ただし“全リモート化”はまだちょっと難しいのが現実かも……。
まとめ
社内SEの仕事は、確かに物理的な作業を伴う場面があります。キッティングや突発対応、打ち合わせなど、現場に足を運ばないと難しい仕事も残っているのが現状です。そのため「完全リモート化」は、少なくとも中小企業の現場では難しいというのが正直なところです。
しかしながら、問い合わせ対応や運用業務の多くは、リモート対応可能なものが増えており、それを支えるのが「仕組み化」です。具体的には、以下のような取り組みが有効です:
- 対応手順のマニュアル化(PDFや動画化)
- 壊れにくく安定した機器選定
- チャットやリモートツールの社内導入
- 一部業務の外注(例:キッティング業者)
これらの整備によって「常駐しなければならない理由」は大幅に減ります。実際に筆者も、複数の会社を担当していながら、拠点間を頻繁に移動することなく業務をこなせています。
社内SEのリモート化には、会社の文化や風土、上司の理解も関わってきますが、それらを言い訳にせず、まずは“自分の手が届く範囲”で工夫を重ねることが大切です。少しずつ環境を整えることで、自分の働き方にも余裕が生まれ、結果的に職場全体の効率も上がるはずです。
社内SEという仕事は「目立たず静かに支える存在」になりがちですが、その内側には、業務改善と仕組みづくりの面白さが詰まっています。リモートという視点からも、もっと自由な働き方を模索していける時代にしていきましょう!
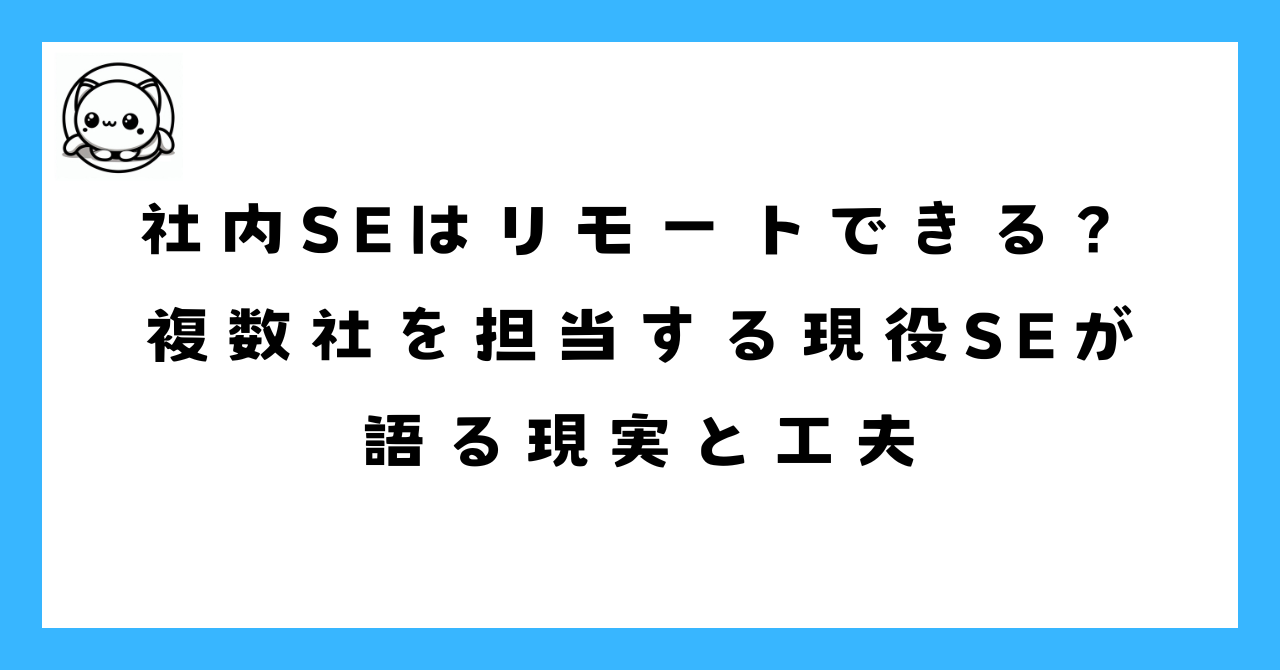
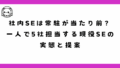
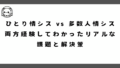
コメント