はじめに
システム担当者や社内SEとして現場と関わっていると、ふとした“呼び方の違い”で伝わらないこと、ありませんか?実はこの呼称のズレ、軽く見ていると業務の混乱や誤解を招く原因になるのです。本記事では、現場でよくある用語の違いと、そのズレを防ぐための実践的なポイントについてご紹介します。
呼称ズレのよくある例
実際にあった例1. 予約システム = LP?
たとえば、ある部署では「予約フォーム付きのページ」を「LP(ランディングページ)」と呼んでいました。マーケティング業界ではLPというと、コンバージョンを目的とした1枚構成のページを指しますが、現場では「予約できるページ」という意味で使われていることがあります。
実際にあった例2. 共有フォルダ = Samba?
「あのファイル、Sambaにありますよ」と言われたけれど、それが「共有フォルダのこと」だと気づくまでに少し時間がかかった、なんて経験はありました。技術的にはSambaはプロトコルやソフト名ですが、現場では「Samba = ネットワークフォルダ」として認識されていることがあるのです。
ズレが生む問題
用語の意味が人によって違うと、認識のズレから指示が通じなかったり、仕様の誤解が生じたりします。最悪の場合、誤操作や誤納品などにもつながりかねません。
どう防ぐ?実践的な対策
1. 訂正よりも周知を優先
細かく訂正しても、現場ではすぐに浸透しないことが多いです。それよりも、現場で使われている呼称を把握し、その前提で設計・周知することで、認識のズレを防ぐ方が現実的です。
2. 用語リストを作成して共有
現場とシステム担当者の間で共通理解を持つために、社内用語リストを作っておくと便利です。たとえば「予約ページ(現場ではLPと呼称)」のように、両方の呼び方を併記しておくのがポイントです。
3. 聞き慣れない単語は都度確認
「それってつまり◯◯ってことですか?」と柔らかく確認するクセをつけておくと、誤解が起こる前に防ぐことができます。聞き返しは恥ではなく、ズレをなくすスキルです。
まとめ
システムの専門用語と、現場での呼称の違いは意外と盲点になりがちです。呼び方が違うだけで、大きなコミュニケーションロスになることもあります。だからこそ、訂正よりも歩み寄り、共通の言葉を育てていく姿勢が、社内SEとして信頼される一歩になります。

「それ、正式名称じゃないけど…まぁ通じてるしOK!」って現場ではよくありますよね。用語のズレも“設計の一部”と考えて、うまくすり合わせていきましょう🧩
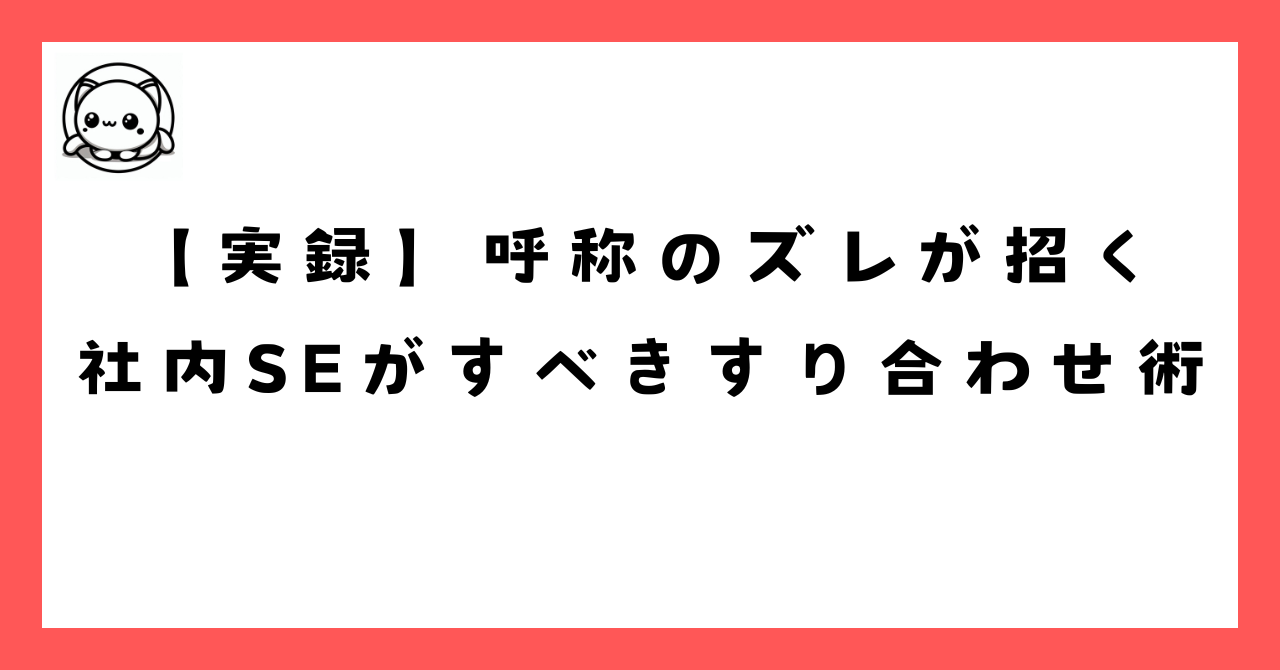
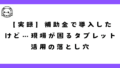
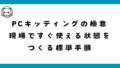
コメント