はじめに
企業のIT部門、いわゆる「情シス(情報システム部門)」の体制は企業ごとにさまざまです。少人数、あるいはひとり情シスで全てを回すケースもあれば、大人数で分業しているケースもあります。今回は、実際にひとり情シスと多数人情シスの両方を経験した立場から、それぞれの利点と課題、そしてチームとしてどうあるべきかについて感じたことを共有します。
ひとり情シスのメリットと限界
すべてを把握できる一体感
ひとり情シスの最大の強みは、全体を俯瞰しながらすべてのシステムやフローに関われる点です。設計から構築、保守まで一貫して行うことで、全体像を把握しやすく、柔軟な対応が可能です。
一方で、リスクは高い
しかし、それは同時に「すべて自分しか知らない」「自分が休めない」状況も意味します。業務がブラックボックス化しやすく、異動や退職時の引き継ぎも困難になりがちです。
多数人情シスのメリットと課題
分業と専門性の強化
チームで情シスを運営することで、それぞれの得意分野を活かして分業が可能になり、作業効率や品質の向上が見込めます。特定分野のスキルに長けた人材がいることで、新技術の導入やトラブル時の対応も迅速です。
属人化の新たな落とし穴
一方で、それぞれが特定の業務や技術に「だけ」携わるようになると、チーム全体での知識共有が進まず、結果的に属人化が進行してしまう恐れがあります。分業が進みすぎると、「その人がいなければ分からない」という状況に逆戻りすることも。
属人化を防ぐために必要なこと
業務の明文化と仕組み化
誰かが「何とかしてくれるだろう」という依存ではなく、業務を文書化し、ナレッジとして共有することが大切です。マニュアル、手順書、FAQなどを用意することで、チーム内での情報の再利用性を高めましょう。
協力する文化を育てる
「これはAさんの担当だから」「Bさんしかわからないから」ではなく、時には一緒に対応したり、ペア作業を行うことで、お互いの理解が深まり、万が一の際にもカバーし合える体制が築けます。
まとめ
ひとり情シスはスピード感と一貫性に優れる一方で、属人化と過負荷のリスクがつきまといます。多数人情シスは分業による効率化が可能ですが、逆に知識の断片化や無関心による属人化も起こり得ます。
どちらの体制にも共通して言えるのは、「属人化は避けなければならない」ということ。IT部門はシステムの安定運用だけでなく、業務の継続性や将来的な改善にも関与する存在です。そのためには、情報の共有、業務の明文化、そしてチームとしての協力体制が必要不可欠です。
また、業務を仕組みに変える工夫も大切です。GASなどの無料ツールを使った業務自動化や、社内Wikiによる情報共有環境の整備など、小さく始めて大きな負担を軽減する「スモールメリット」の考え方が、今後の情シスにとって鍵となるでしょう。
ひとりでも、チームでも、目指すのは「いつでも誰でも対応できる」情シス体制。属人化に悩む方のヒントになれば幸いです。

多数人のころは、仕事が分かれて楽になったけど「俺しかできない」仕事が増えないように気をつけてます💦 チームって、意識しないとチームにならないんですね。
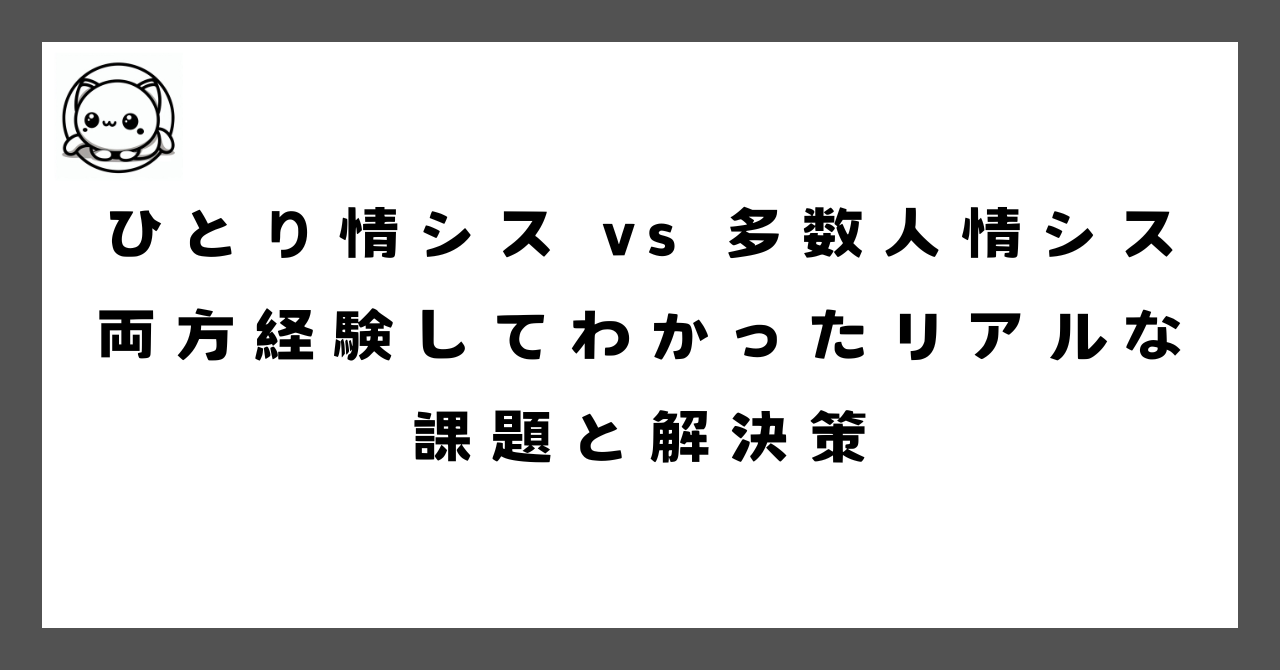
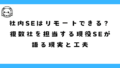
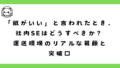
コメント