はじめに
「とりあえずシステムを入れれば解決する」──そんな考え方で導入されたツールが、現場で十分に使われず放置されているケースをよく見かけます。ITシステムはあくまで“道具”です。道具である以上、使う人が目的に応じて適切に選び、活かすことが重要です。
この記事では、システム導入の本質と、業務改善に本当に役立つ「道具としてのITシステム」の選び方・活かし方について解説します。
システム導入の目的を見失わない
1. 現場の課題を起点にする
システム導入の出発点は、現場の「困りごと」や「もっとこうしたい」という声であるべきです。目的が不明確なまま導入されたシステムは、結局使われず、コストやリスクだけが残ります。
2. 機能重視ではなく“使い方”重視へ
機能が多い=優れたシステムではありません。使いやすさや導入のしやすさ、運用の負荷の低さなど、「継続的に使えるかどうか」が重要な判断軸になります。
ITシステムは“使ってこそ意味がある”
1. 道具としての認識を持つ
システムは目的を達成するための手段=道具です。目的を見失うと、導入したことに満足して終わってしまいがちです。まずは「何のためにこの道具を使うのか?」を明確にしましょう。
2. 運用者が主役であるべき
現場で使う人たちの声を取り入れないと、システムは形骸化します。社内SEや情シス担当者は「現場の声の代弁者」として、導入の前後でフォローを行うべきです。
業務効率化とユーザビリティの両立
1. 効率化は手段であり、目的ではない
「効率化」という言葉にとらわれすぎると、現場の実態に合わない仕組みを押し付けてしまうことがあります。目的は、業務の質を上げること。効率化はそのための一手段にすぎません。
2. ユーザビリティを無視しない
どんなに高機能でも、使いにくければ定着しません。UIや操作性、シンプルな導線設計が、日常の業務における“使いやすさ”に直結します。
まとめ
ITシステムは目的を達成するための“道具”です。導入する際は、機能や価格ではなく「本当に必要とされているか」「現場で使われ続けるか」を重視すべきです。社内SEや情シス担当者は、導入後のフォローも含めて“システムの定着”を意識した対応が求められます。

私も過去に「とりあえず便利そうだから導入!」っていう失敗をしたことがあります…😅
でも、“使いやすい道具”として選ぶようにしてから、現場の反応も変わりましたよ!
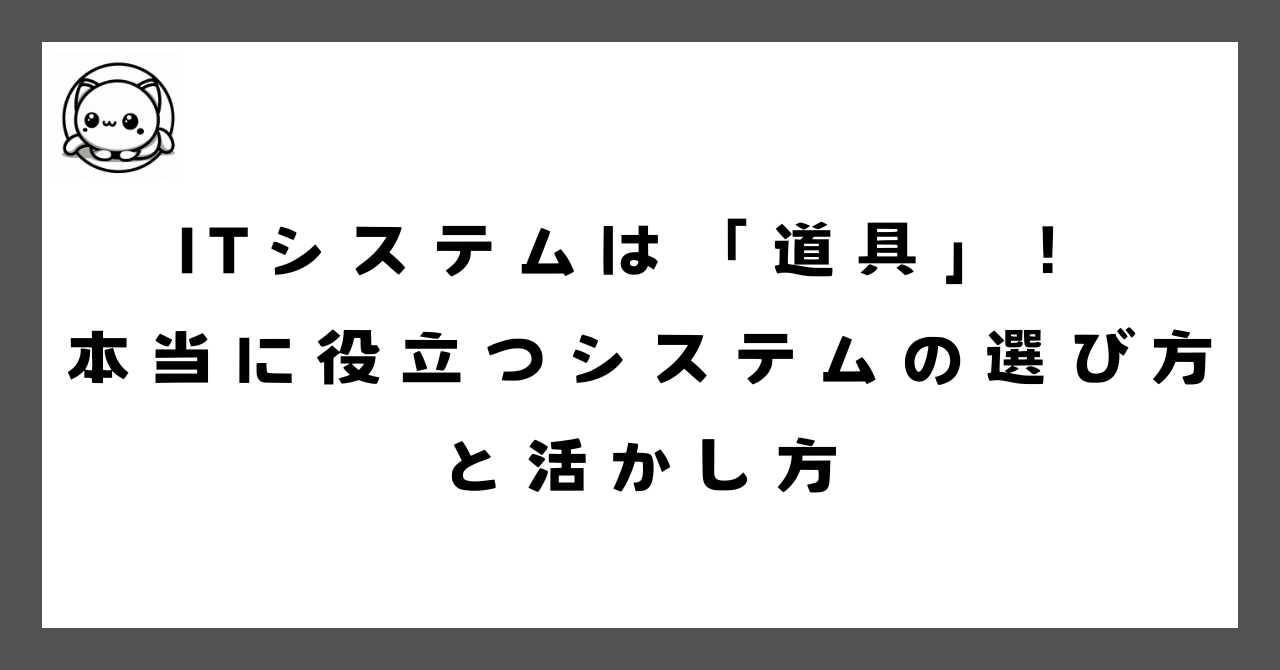
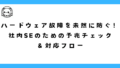

コメント