IT機器の対応年数とリスク管理
はじめに
企業の現場では、驚くほど長期間にわたって同じIT機器が使われ続けているケースが少なくありません。メーカーの推奨寿命を超えて使用されている機器が、果たしてどれほどのリスクを抱えているのか、現場の社内SEとしては把握しておく必要があります。
メーカーの推奨年数とは?
一般的な対応年数の目安
多くのIT機器には、メーカーが推奨する使用年数やサポート期限が設定されています。以下はその一例です:
- ノートPC・デスクトップPC:4~5年
- サーバー:5~7年
- ネットワーク機器(ルーター・スイッチなど):5年程度
- プリンタ・複合機:5~7年
この期間を過ぎると、部品供給の停止やソフトウェアのサポート切れが発生し、業務に支障をきたす可能性が高まります。
なぜ現場では長期間使用されるのか?
使えているから買い替えない
「今のところ問題がないから」という理由で、10年以上同じPCやサーバーを使い続けている現場は少なくありません。特に中小企業では予算が限られており、明確なトラブルが発生しない限り、買い替えの稟議が通りづらいのが現実です。
買い替え提案のハードル
使用中の機器がまだ稼働している状態では、管理者側が買い替えの必要性を説明するのは難しい場合があります。しかし、リスクを放置すれば、ある日突然業務が停止するリスクを抱えることになります。
社内SEがとるべき対策
1. 定期的な棚卸しと記録の更新
まずはすべてのIT機器の使用開始日や設置場所、稼働状況を記録し、定期的に棚卸しを行うことが重要です。これにより、老朽化リスクのある機器を可視化できます。
2. リスク評価と買い替え計画の策定
「まだ使える」ではなく、「いつまで安心して使えるか?」という視点で、リスクの高い機器から優先的に更新を検討しましょう。機器の故障率や業務影響の大きさも判断基準になります。
3. 稟議が通りやすい資料づくり
管理部門や経営陣に納得してもらうために、「使用年数の限界」「サポート切れの影響」「過去の障害実績」などを資料にまとめ、段階的な更新計画として提案することが効果的です。
まとめ
IT機器の寿命を過ぎたまま使い続けることは、単に古い設備で業務を回しているというだけではありません。企業にとって大きなリスクをはらむ「時限爆弾」となりうるのです。現場にトラブルが起きてからでは遅く、原因調査や復旧対応に追われ、機会損失や信頼低下を招くこともあります。
特に、2025年の崖が叫ばれる中、社内SEの役割はますます重要になっています。老朽機器の見直しはDXの足かせを取り除く第一歩でもあり、小さなことからでも進めていくことが企業の未来を守る道になります。
まずは台帳の作成から、小さく、でも着実に始めてみましょう。設備投資は「攻めのIT投資」ではなく、「守りの経営戦略」でもあります。

ウチのファイルサーバー、実は12年モノだったんですよね…。調子悪くなってからじゃ遅いので、買い替えの計画をこっそり進めてます💦 少しずつ準備するのがポイントです!
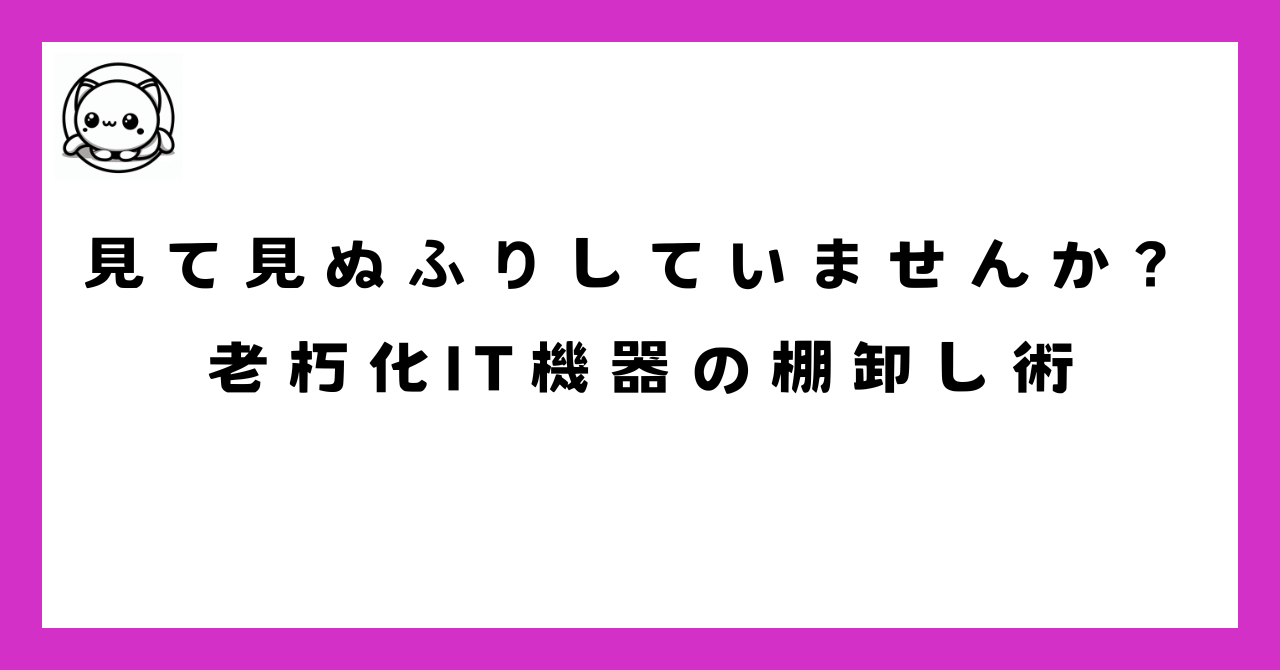
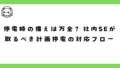
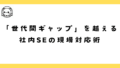
コメント