はじめに
私はこれまで、受託開発を行うシステム会社と、企業内で情報システム部門に所属する社内SEの両方を経験してきました。どちらもITエンジニアという共通点はありますが、実際の働き方や意識には大きな違いがあります。
本記事では、両者を経験して見えてきた「仕事の違い」「関わり方の温度差」「向き・不向き」について、現場目線でお伝えしていきます。
社内SEは“全体を見る”仕事
社内SEの仕事は、単にシステムを作ることではありません。経理、人事、営業、製造、物流など、会社のあらゆる部門と連携し、それぞれの業務フローや課題を深く理解したうえで、「業務改善」の視点でシステムを設計・運用していく必要があります。
“誰かの問題”では済まされない
「この作業、ミスが多いな」「時間がかかってるけど、根本の原因は?」「もっとうまいやり方はないか?」――こうした問いに向き合うのが、社内SEです。導入後の運用フォローも長期的に関わるため、他人事にはできません。

日々の運用で困っていることに“気づける”のも社内SEの強みだと思います!ただ動くものを作るだけではなく、「その後も安心して使えるか」が大切ですね。
システム会社の役割と立ち位置
一方、システム会社では「システムを作ること」が契約の目的です。顧客企業の業務にはあまり踏み込まず、仕様書通りに開発する、または要件定義を元に画面や処理を実装するのがメインの仕事になります。
部署によっては“会話ゼロ”も
私が在籍していたときは、客先とのやり取りを担当営業が担っていたため、開発側はほとんどコミュニケーションに関与しませんでした。「ただひたすらコードを書く」という状態で終わる案件も珍しくありません。

「誰のために何を作っているか」が分からないまま終わると、正直ちょっと寂しいですよね。技術を磨くにはいいけど、やっぱり使ってくれる人と話したいな〜って思っちゃいます。
私が社内SEを選んだ理由
結局のところ、「自分は何がしたいのか?」という問いに戻ってきます。私の場合は、システムの完成よりも「それを使ってくれる人との会話」のほうが楽しかったんです。もちろん、営業のように上手にプレゼンできるわけではありません。でも、“ありがとう”の言葉や、ちょっとした改善で喜んでもらえる瞬間が何より嬉しくて、社内SEという働き方を選びました。
まとめ:技術だけじゃない、関係性で変わる働き方
システム会社と社内SE、どちらが良い・悪いという話ではなく、それぞれの役割と働き方に違いがあります。技術の深掘りがしたいならシステム会社、業務改善や人とのつながりを大切にしたいなら社内SEが向いているかもしれません。
私は「現場と会話しながら、使いやすい仕組みを一緒に作る」ことに魅力を感じました。だからこそ、今日も社内の誰かの“困った”に寄り添えるよう、現場を歩きながら仕事をしています。

エンドユーザーとの距離が近いのって、ほんとにやりがいありますよね!いろいろ相談されることもあるけど、その分、現場に役立ってる実感があるからがんばれます💪
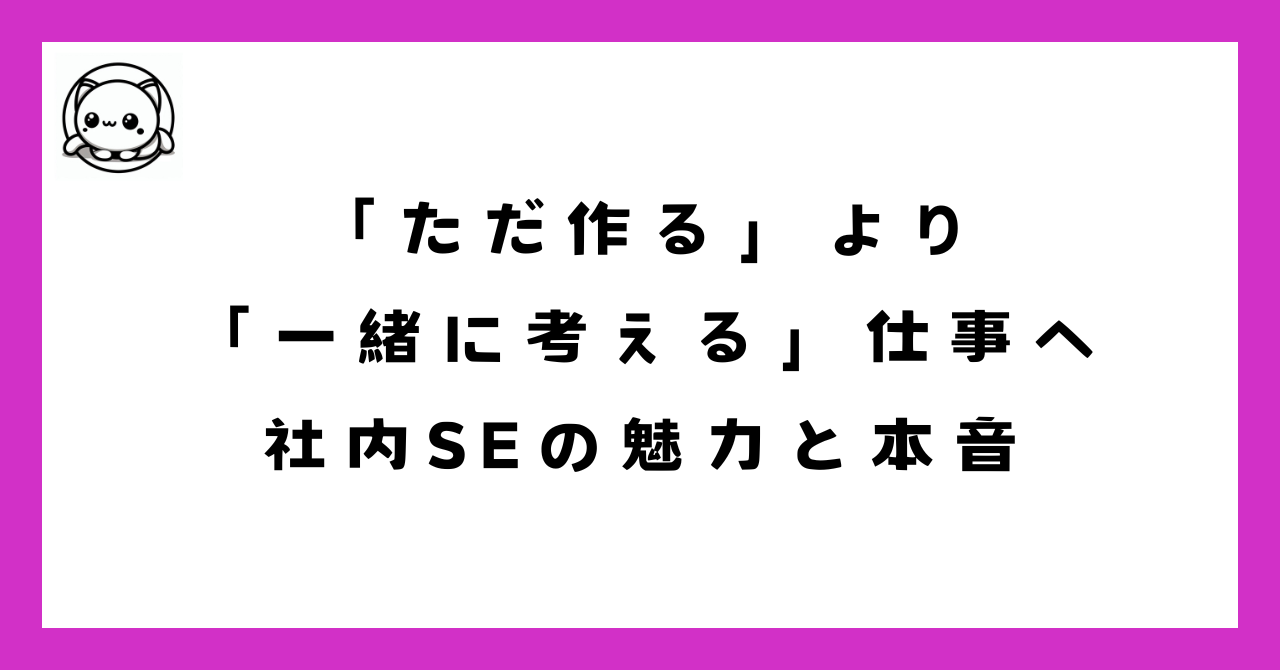
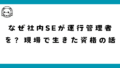
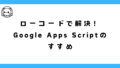
コメント