はじめに
「DX(デジタルトランスフォーメーション)」という言葉が流行してから数年が経ちます。多くの企業がDX推進室を立ち上げ、RPAやAI導入に取り組んできました。しかし現場からは「結局何が変わったの?」「やるだけやって終わった」といった声が聞こえてきます。本記事では、現場にDXが浸透しない理由、そして一過性で終わらない“続く改善”を生み出すための視点を、社内SEの立場から掘り下げていきます。
DXの本来の意味とは
DXは単なるIT化や自動化ではなく、企業文化やビジネスモデルそのものを変革し、顧客価値を再定義する取り組みです。つまり、「仕組みを作る」ことがゴールではなく、「その仕組みを活かして、新しい価値を生む」ことが本質です。
しかし現場では、業務ツールの刷新や自動化の導入をもってDXと勘違いされているケースも多く、「導入だけで満足して終わる」現象が頻発しています。
現場にDXが浸透しない理由
- 目的が曖昧:「DXをやれ」と言われて動いているだけで、何のために何を変えるのかが不明確
- 現場との乖離:経営やIT部門主導で進み、実務に合っていない施策が多い
- 成果の見えにくさ:変化を実感できず、結果的に「面倒なだけ」と認識される
- 担当者の固定化:属人的になり、担当が抜けると改善が止まる
つまり、DXの失敗とは「ITツールが悪かった」のではなく、「導入の目的や構造」がずれていたことが原因である場合が多いのです。
“続かない改善”を止めるために
一時的なツール導入や、限られた部署だけの試験運用では、業務の本質的な改善にはつながりません。以下のような視点を持つことで、改善が継続し、現場の力として定着していきます。
- 現場の困りごとからスタートする
トップダウンではなく、「なにが面倒か」「なにが時間を食っているか」など、現場の声から改善ポイントを洗い出します。 - 小さく始めて、すぐ試す
完全なシステムではなく、GASやExcelマクロなど身近な手段でPoC(概念実証)を行い、効果と反応を観察します。 - 成果の“見せ方”を工夫する
数字や画面キャプチャ、利用者の声などを可視化し、他部署へも波及できる材料とします。 - 属人化を防ぐ仕組みを用意する
マニュアル、コードコメント、動画解説などを使い、担当が変わっても継続できる設計を心がけます。
まとめ:DXを“自分ごと”にするには
DXが続かない理由は、導入したツールや技術にあるのではなく、それを「使いこなす主体」がいないことにあります。特に現場の実務者が置いてけぼりになり、「IT部門が勝手にやっていること」と思われた時点で、DXは“外のもの”になってしまいます。
大切なのは、「自分の業務がどう変わるか」「なぜやる必要があるのか」を本人が理解し、納得できるように設計することです。そのためには、現場への“参加”と“共創”の仕掛けが必要です。
たとえば、ツール選定に現場の代表者を巻き込んだり、改善結果を社内ポータルで共有するだけでも、「他人ごと」だったDXは「自分たちの話」になります。
DXとは派手な改革ではなく、「日々の業務を少しずつ、無理なく良くしていく」積み重ねの延長線上にあるものです。現場が自走し、改善を継続できる文化を育てることが、真のDXといえるのではないでしょうか。

DXって、正直「なんかすごいこと」って思いがちだけど、現場の“面倒”に真剣に向き合うことから始まるんですよね。小さくても本質をついた改善こそ、続くDXだと思います😊
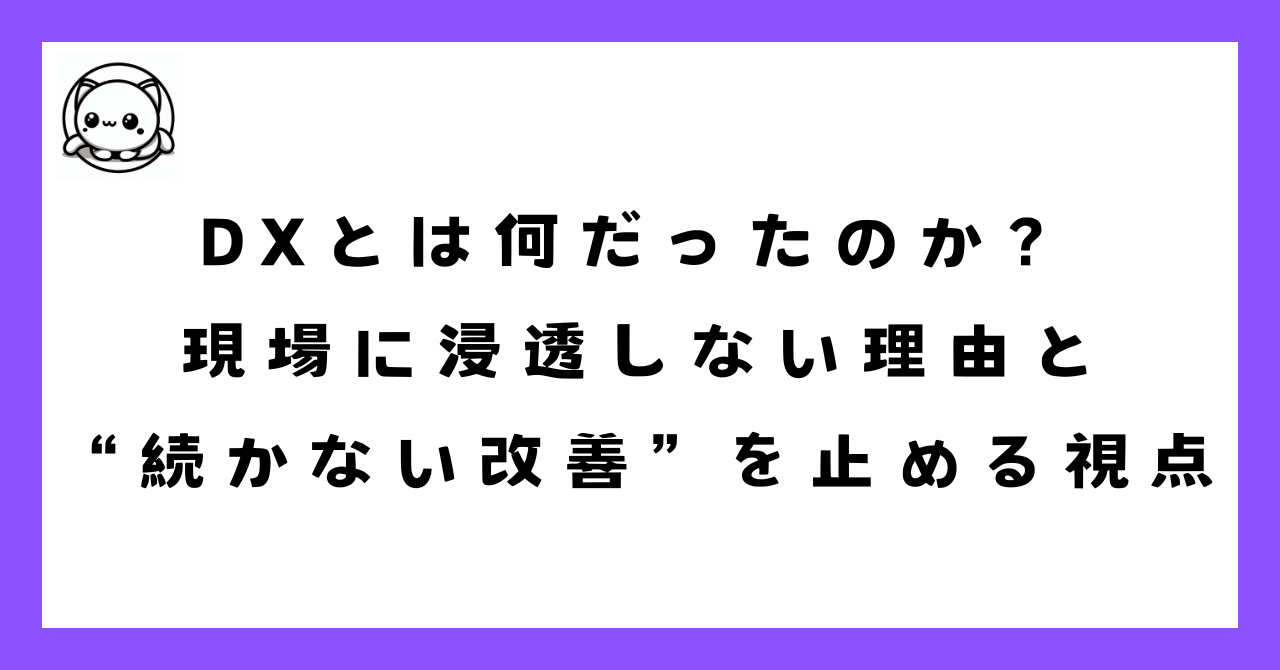
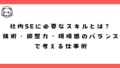
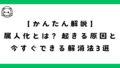
コメント