はじめに
社内SEは社内のIT全般を担うポジションですが、「デザイナー業務も担当すべきなのか?」という議論が現場で出てくることがあります。この記事では、社内SEがデザイン業務を担うべきかどうかを軸に、現場で求められる役割や工夫の余地について解説します。
社内SEは基本的にデザイナーではない
専門性の違い
社内SEは、業務システムの運用・保守、インフラ整備、業務改善などを中心に活動します。デザイナーは、UI/UX設計やビジュアル表現を専門とする職種であり、スキルセットも異なります。従って、基本的には両者は別の職種であるべきです。
最低限のUI調整は求められる
使いやすさの配慮は必要
たとえば、Google フォームや社内ツールのUIであっても、文字の詰まりや配色、操作のしやすさなど、最低限の見た目の配慮は求められます。ユーザーが迷わず使えるようにすることは、SEとしての責任の一つといえるでしょう。
テンプレートやノーコードツールの活用
Canva や Figma、Notion などのツールを使えば、デザイン経験が少なくても「そこそこ見栄えのする」資料やUIを作ることができます。テンプレートを活用することで効率も上がり、現場からの信頼も得られやすくなります。
提案できると、さらに価値が上がる
外注コストを削減できる提案
簡易的なバナーやフォーム画面の調整程度であれば、「デザイナーに外注するほどではないけど、自分たちでは対応できない」場面も多いです。そうしたときに、Canva等で対応できる旨を提案すれば、外注費削減にもつながります。
提案する姿勢が評価される
「ここまでなら自分で対応できます」と事前に線引きをしたうえで提案する姿勢は、社内での信頼にもつながります。完璧なデザインではなくても、業務改善の一環として「見せ方」にも気を配ることが、社内SEの価値を高める一歩になります。
まとめ
社内SEの本業は、IT環境の維持管理と業務改善です。デザイナー業務は原則含まれません。しかし、社内ツールや資料の「最低限のUI改善」には関わるべきであり、ノーコードツールを活用することで、現場の使いやすさを担保することが可能です。
また、「ちょっとしたデザイン業務」を自分で対応することで、外注費削減というコスト面のメリットを企業にもたらすことができます。Canvaなどを使った軽微な調整を提案できれば、社内SEとしての提案力・企画力も評価されるでしょう。
最終的には、自分の守備範囲を正しく認識し、無理に全てを抱え込まないことが大切です。あくまで「できる範囲で工夫する」「提案できることは提案する」という姿勢が、これからの社内SEに求められていくでしょう。

「それ、ちょっとだけなら自分で作りますよ!」って言えるとカッコいいですよね。Canvaってほんと便利です…!見た目も業務効率も、ちょっとした工夫で変わると思います😊
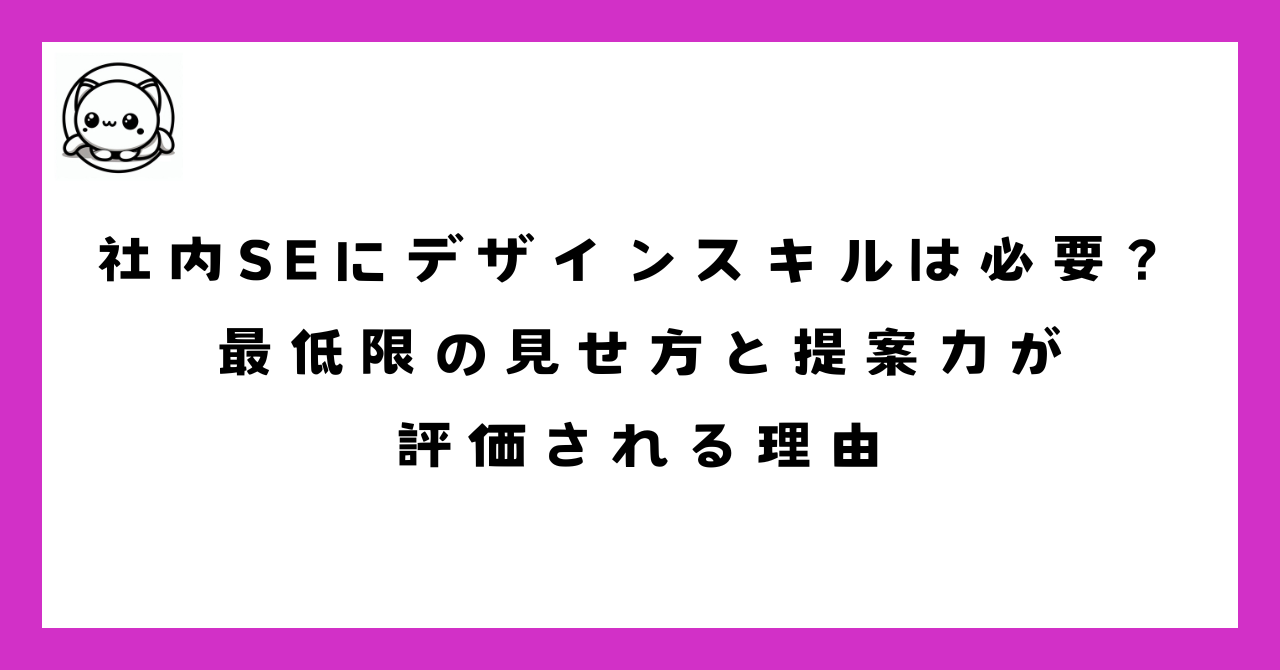
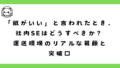
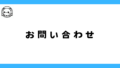
コメント