はじめに
生成AIや機械学習などの技術が急速に進化する中で、社内業務へのAI活用が現実味を帯びています。「AIって難しそう」と感じる方も多いかもしれませんが、実は無料や低コストで導入できる方法も多く、社内SEにとって大きな武器となる可能性があります。
本記事では、社内業務でAIを活用する方法、実際の自動化事例、導入時のメリット・注意点について、わかりやすくご紹介します。
社内業務でAIを活用するには?
1. チャットボットによる問い合わせ対応
社内からのよくある質問や、マニュアルの問い合わせ対応をAIチャットボットに任せることで、担当者の負担を大きく軽減できます。例えばGoogle Apps Scriptと連携することで、LINEやSlackとつなげて即時対応を実現できます。
2. AI OCRを活用した書類のデジタル化
紙の書類やPDFの読み取りにAI OCR(文字認識技術)を使うことで、手作業による入力の手間を大幅に削減できます。Google Cloud Vision API や freeeのOCR機能など、業務に応じたサービスが活用可能です。
3. ChatGPTを使った文章生成・要約
議事録や報告書、メール文面の下書きなど、文書作成にかかる時間を短縮する手段としてChatGPTが有効です。API経由で社内ツールに組み込むことも可能で、GASやPythonとの連携も現実的です。
AI活用の具体的な事例
事例①:部門間調整の自動化
営業部からの依頼をAIチャットボットが受け取り、必要な情報を整理して総務や経理へ自動通知。これにより、やりとりの手間や確認漏れが減少しました。
事例②:Excel業務のGAS自動化+AI要約
日次レポートの集計・要約をGASで自動処理し、ChatGPTで文章を整えるワークフローを構築。報告業務の時間が1/3に削減された事例もあります。
事例③:問い合わせ履歴の分類・分析
LINE公式アカウントからの問い合わせ履歴をAIで分類し、よくある質問や対応パターンを可視化。対応マニュアルの改善にもつながりました。
AI導入のメリットと注意点
メリット①:人的負担の軽減
ルーチン業務をAIに任せることで、担当者はより付加価値の高い業務に集中できるようになります。働き方改革や定時退社にも貢献します。
メリット②:ナレッジの蓄積と活用
AIは業務の中で収集されたデータを活用して精度を高めていくため、ナレッジの可視化・標準化にもつながります。
注意点①:情報の取り扱いとセキュリティ
外部APIを利用する場合は、社内データの取り扱いやプライバシーへの配慮が必要です。機密性の高いデータには特に注意しましょう。
注意点②:過信しすぎない
AIはあくまで補助的なツールです。判断が必要な場面では人間の確認を挟むなど、適切な運用ルールの整備が重要です。
まとめ
AI技術は社内SEにとって、もはや特別なものではなく、日々の業務に自然に組み込めるツールとなりつつあります。「いきなり導入」は難しくても、「小さく始めて効果を実感」することで、業務改善の大きな一歩となるはずです。

「AIなんてウチにはまだ早い…」と思ってました。でも、GASやChatGPTを少し使うだけでも、業務がすごくラクに!小さく試してみるだけで、本当に世界が変わりますよ〜✨
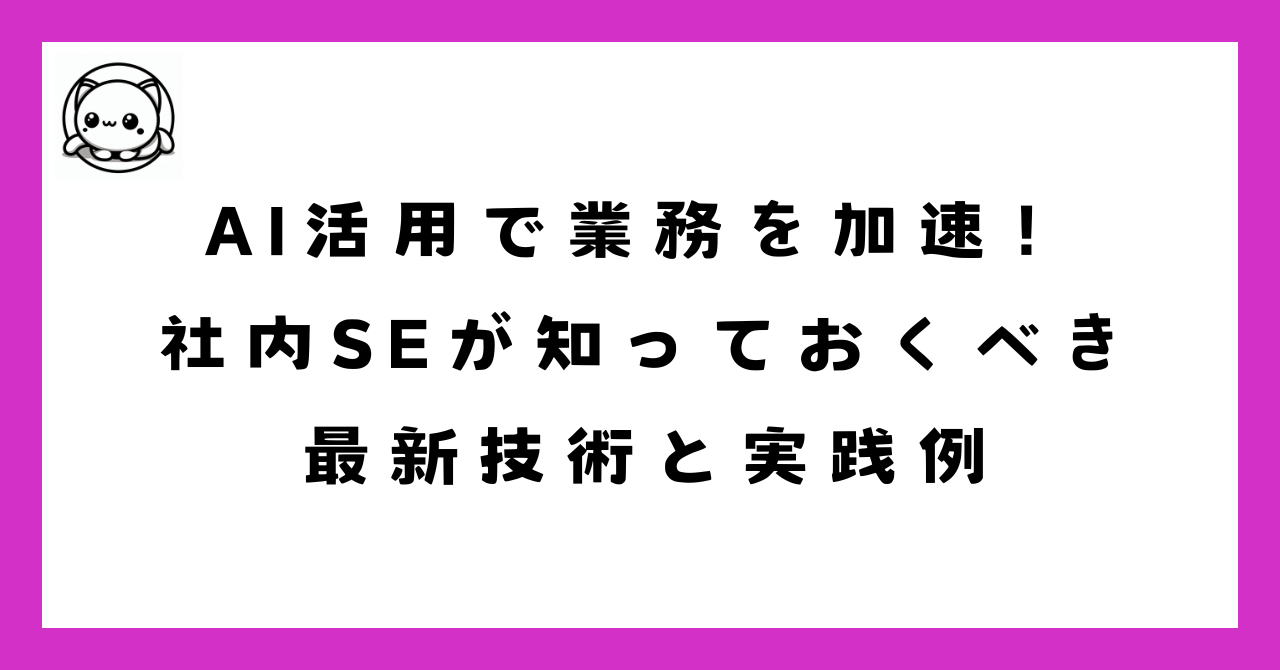

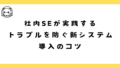
コメント