はじめに
「これ、すぐできるでしょ?」「なんとか今日中にお願い」といった“無理難題”に、社内SEとしてどう対処すべきか。相手の要望を真正面から否定できず、気づけば疲弊してしまう――そんな経験をしたことのある方も多いのではないでしょうか。
本記事では、断りづらい状況でも角を立てず、誠実に対応できる「ふわっと断る技術」を5つ紹介します。「できません」を上手に伝える方法は、社内SEの持続可能な働き方を支える大事なスキルです。
1. 相手の意図を聞き返す
要望が来たら、すぐにNoを言うのではなく、「どんな背景ですか?」「最終的にどんな状態が理想ですか?」といった質問を投げ返しましょう。これによって、単なる“要望”から“課題”に置き換えることができ、そもそも解決方法が別にあるケースも多いです。
2. 一部だけ引き受けてあとは提案
「このままだとできませんが、ここまでは対応できます」と“ワンクッション”を入れることで、相手も感情的にならず、協議の余地が生まれます。たとえば、「自動化は難しいけど、テンプレートだけは作っておきますね」と部分的に対応する手法です。
3. 優先度の一覧に加える
自分のタスク管理リストやチームの「対応中一覧」を見せ、「このような優先順位になっているため、すぐには対応できません」と説明します。視覚化によって「できない」ではなく「順番がある」という形に変換できます。
4. 第三者の名前を借りる
「情報セキュリティ上、この件は統括の確認が必要で…」「上長から保留の指示が出ていまして」など、ワンクッション置く形で断るのも有効です。自分が悪者にならずに済むほか、正式なルールに立脚した伝え方となるため説得力があります。
5. 別案を提示する
単に「できません」ではなく、「代替案としてこういう方法もありますがどうですか?」と提案することで、協調的な印象を与えることができます。実際、無理難題の多くは“本当に必要な目的”が明確になっていないことが多く、別の手段でも十分なことが多いです。
まとめ
社内SEという立場は、「断りにくい依頼」が日常的に発生する職種です。IT知識に差があるため、相手は悪気なく“無理な要求”をしてくることもあります。そんなとき、真面目にすべてを引き受けようとすれば、自分が潰れてしまい、結果的に組織にも損失となります。
だからこそ、「できません」と言うことは“逃げ”ではなく“誠実な判断”であることを自分に許してあげることが重要です。ただし、冷たく断るのではなく、相手の立場を尊重しながら“やさしく境界線を示す”スキルを持つことで、信頼はむしろ高まります。
本記事で紹介した5つの技術は、すべて「断るための方法」ではなく、「より良いコミュニケーションを通じて、現場全体の課題解決力を高める手法」でもあります。すぐに実践できるものから試して、あなたなりの“ふわっと断る”スタイルを確立していきましょう。

「無理です」って言うのは勇気がいりますが、断り方にも“技術”ってありますよね。現場を守るには、やさしく上手にNOと言える力がほんとに大事です😊
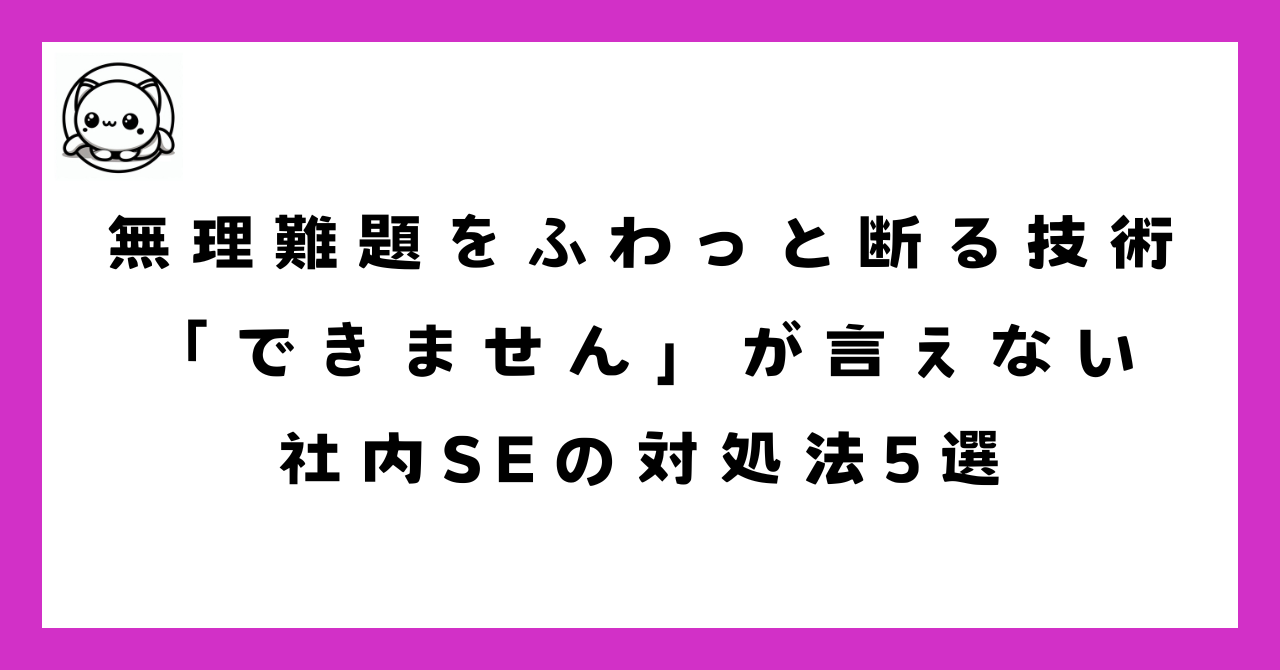
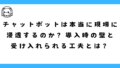
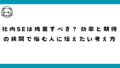
コメント