はじめに
同じ業務をしていても、「指示を待つだけの人」と「自ら動ける人」では、成果も評価も大きく変わります。社内SEとして複数の現場を見てきた筆者の視点から、「やらされ社員」と「自走社員」の違いを、実際の働き方や現場の反応を交えて解説します。
表面的な働きぶりではなく、“なぜその行動になるのか”という背景にこそ、現場での課題や改善のヒントがあります。
“やらされ社員”とは何か
受け身で、行動が止まりがち
指示がなければ動かず、業務改善の意識も低い。よく聞く「やらされ感」を持つタイプです。SEがいくら便利な仕組みを作っても、「教えてもらってないから使わない」「忙しいから今は無理」という反応で終わってしまいます。
非効率の温床になりやすい
このタイプの社員が多いと、システム導入や改善が進みません。結果的に、SEの仕事も「マニュアル対応」「問い合わせ処理」に追われ、本来やりたい仕組み化ができなくなります。
“自走社員”とは何か
自ら課題を発見し、動ける
「これ、もう少し効率化できませんか?」「こういうの作ってみたんですが」――そんな声が上がる現場では、社内SEとの協業もうまくいき、業務改善も進みます。まさに“現場と一緒に走れる”状態です。
たとえば、ある店舗ではExcelの在庫表に自前のマクロを組んでいた担当者がいました。こちらがAccessの在庫管理システムを提案したところ、その人はすぐに仕様を読み込み、テスト運用にも積極的に関わってくれました。こうした“自走タイプ”の存在は、SEとしても非常に助かります。
改善の連鎖が生まれる
自走型の社員は、他のメンバーにも良い影響を与えます。1人が改善に動けば、周囲も「真似してみよう」となり、現場全体が活性化するのです。これは、社内SEから見ても非常にありがたい環境です。
社内SEとしてできること
“やらされ”を“自走”に変える仕掛け
ポイントは、「仕組みで背中を押す」ことです。たとえば、Googleフォームの事例共有や、Notionでのマニュアル一体化など、“自分でできるように見せる”工夫が有効です。
他にも、「操作動画を30秒で終わる形にする」「テンプレートを2クリックで使えるようにする」など、物理的にも心理的にも“始めやすい導線”を用意してあげることがポイントです。
提案できるSEは信頼される
現場に対して「やらせる」のではなく、「選べるようにする」「やってみようと思えるようにする」。この視点を持てるSEは、現場からも一目置かれる存在になります。
まとめ
“やらされ社員”と“自走社員”の違いは、最終的にはマインドセットですが、職場の環境やシステムの仕組みもそれを左右します。社内SEとしては、現場が自走できるような環境・ツール・支援を整えることで、間接的に「自走化」に貢献できます。
全員を一気に変えるのは難しくても、「動ける人を応援する」「見せ方を工夫する」だけで、現場の空気は少しずつ変わっていきます。小さな仕掛けが、大きな改善につながるかもしれません。
あなたの現場には、どんな“動ける人”がいますか?その人が動きやすくなるよう、SEとしてのアシストをぜひ工夫してみてください。

「それ、ちょっとだけなら自分で作りますよ!」って言えるとカッコいいですよね。Canvaってほんと便利です…!見た目も業務効率も、ちょっとした工夫で変わると思います😊
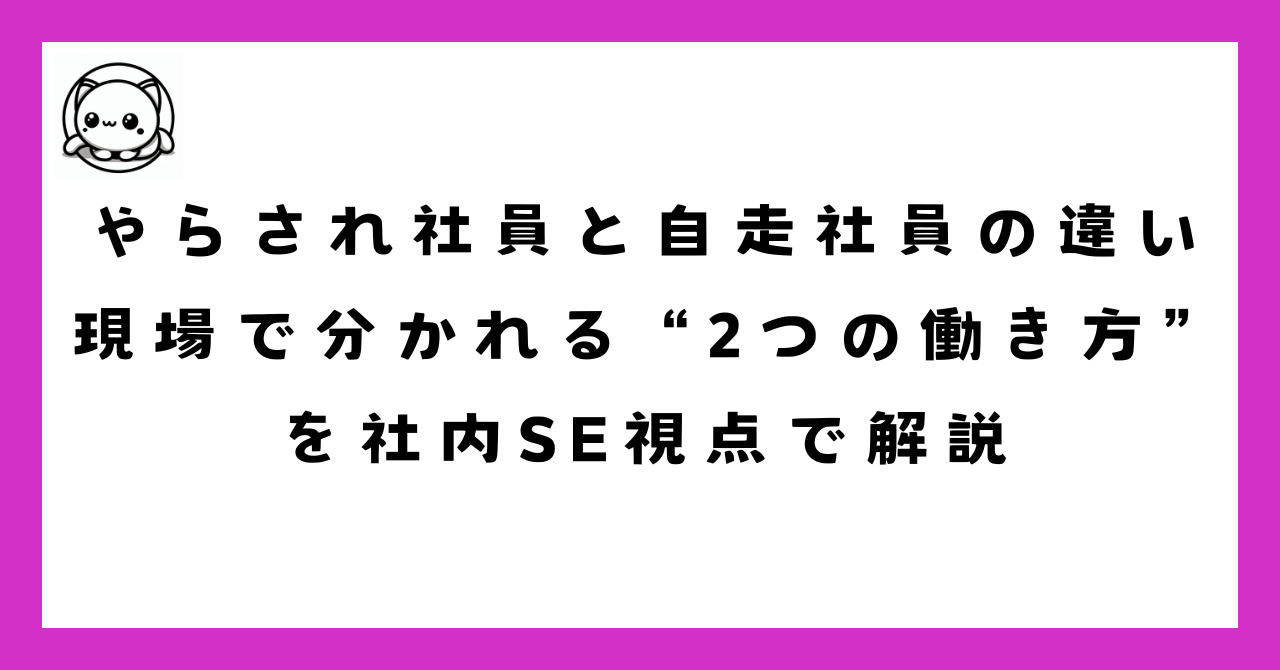
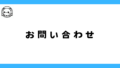
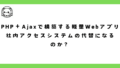
コメント